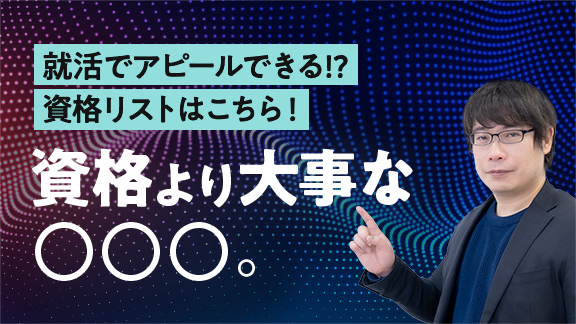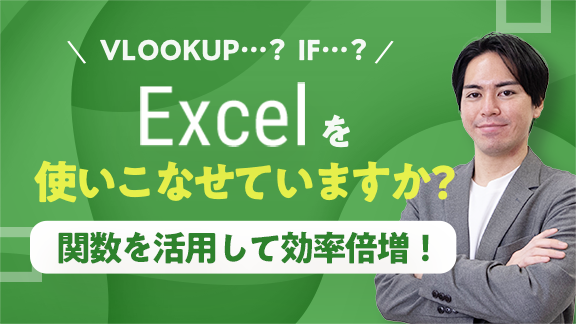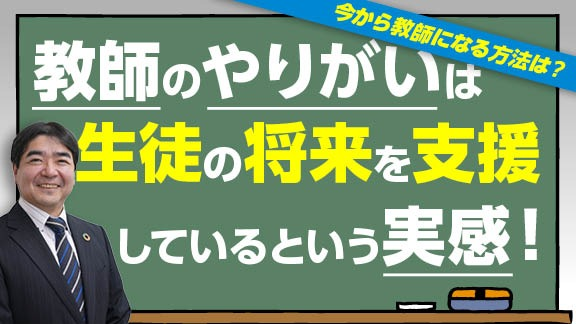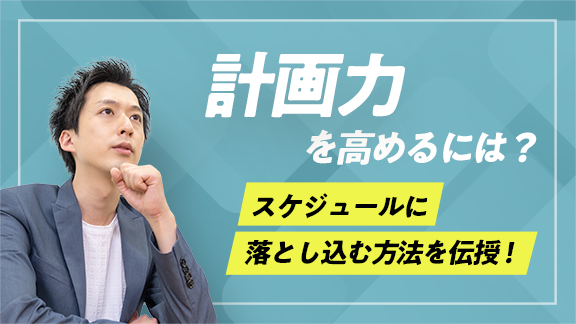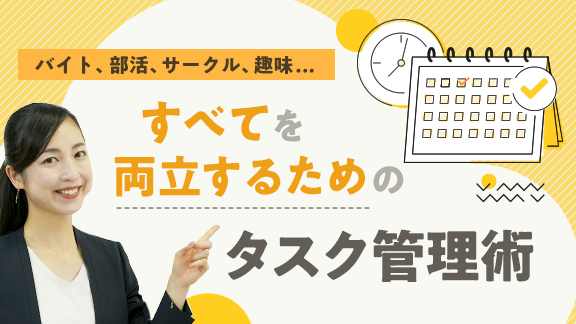大学生におすすめの資格15選!資格取得のメリットや就活・キャリアでの活かし方を解説
- 公開日
- 2025/03/07
この記事は6分で読めます

「資格を多く保有していると今後の就職活動で有利に働く」と考えている人は多いのではないでしょうか。たしかに資格が有利になるシーンもありますが、保有している資格が多いからといって企業からの評価が高まるとは限りません。
この記事では、大学生におすすめの15の資格をご紹介します。また、資格取得を目指す際のポイントや取得するメリットについても解説します。
資格取得を検討している人は、ぜひ以下の講座も併せて参考にしてみてください。
My CareerStudyの動画講座ではアカウント登録をすることで誰でも無料で社会で役立つ知識やスキルを身につけることができます。
1.資格取得は就職活動に有利になる?

前提として、資格を持っていることが必ずしも就職活動を有利に進める決定的な要因となるわけではないことに注意しましょう。
例えば、就職活動で語学力をアピールする際にTOEICの点数が評価されることはありますが、TOEICの点数が高いという理由のみで内定が出るわけではありません。
ただし、その資格を取得した動機や、資格取得という目標のために計画的に行動し目標を達成した経験、将来就きたい仕事への関心の高さなどを示す要素として、資格取得が有利に働く可能性はあります。
つまり、就職活動のために資格を取得するのではなく、あなた自身が今後活躍・成長するために資格の取得を目指すとよいでしょう。
2.大学生におすすめの資格15選

ここからは、大学生のうちに取得しておくことで将来に役立つ可能性が高い資格をご紹介します。興味・関心のある資格がないか一緒に見ていきましょう。
①TOEIC
多くの大学生が思い浮かべる資格の一つがTOEICではないでしょうか。グローバルに展開する企業に対しては、TOEICの点数が高いほど英語力の証明となります。海外での仕事の機会が優先的に得られる可能性もあるでしょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | オフィスや日常生活における英語でのコミュニケーション能力を測る、世界160ヵ国で実施されているグローバルスタンダードな資格 |
| 合格率や難易度 | 合格・不合格ではなくスコア(990点満点)で表示される |
| 試験実施時期 | 毎月1〜2回の頻度で実施 |
| 受験にかかる費用 | 7,810円〜1万450円程度 ※受験する内容によって変動 |
| 勉強時間の目安 | さまざまな場面で支障なく意思疎通ができるレベルを700点とした場合、950時間〜1,200時間程度(1日3時間の勉強を約1年程度継続) |
将来、海外やグローバルに展開する企業で働いてみたい人は、ぜひ以下の講座も併せてご覧ください。
②ITパスポート
ITパスポートは情報系資格の入門的な位置付けで、昨今の情報社会で求められる基本的な知識を身に付けていることを証明する資格です。具体的には、以下のような知識が問われます。
- 新しい技術(AI、ビッグデータ、IoTなど)
- 経営全般(経営戦略、マーケティング、財務、法務など)の知識
- IT(セキュリティ、ネットワークなど)の知識
- プロジェクトマネジメントの知識
大学によっては資格を取ることで単位も取得できたり、IT関連の仕事に就職する際に基礎知識を備えていることのアピールとなったりします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | ITに関する幅広い分野の基本的な知識を有することを証明する資格 |
| 合格率や難易度 | 約50% |
| 試験実施時期 | 月に3回程度、全国の会場で実施 |
| 受験にかかる費用 | 7,500円 |
| 勉強時間の目安 | 100時間〜180時間程度 |
IT業界の仕事内容は以下の講座で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
③基本情報技術者試験
ITエンジニアとして活躍することを目指している人におすすめの資格として「基本情報技術者試験」があります。この資格を取得しておくことで、ITの基本的な知識やスキルが身についていることを証明できます。広範囲のITスキルを学べるため、ITエンジニアとして活躍するための土台を作れるでしょう。ITエンジニアの登竜門ともいわれています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | ITを活用したサービス、製品、システムおよびソフトウェアを作る際に必要な基本的な知識・技能をもち、実践的な活用能力を身に付けていることを証明する資格 |
| 合格率や難易度 | 約40% |
| 試験実施時期 | 月に1回程度 |
| 受験にかかる費用 | 7,500円 |
| 勉強時間の目安 | 50時間~200時間程度 |
ITエンジニアの仕事内容を詳しく知りたい場合は、以下の講座を参考にしてみてください。
④商工会議所簿記検定
商工会議所簿記検定(簿記)は、経理・会計、利益率、コスト管理など企業の数字に関わる知識を習得するための資格で、2級までは独学でも大学生の間に取得しやすいです。就職活動においては、志望企業の経営状態を把握するのに役立ちます。
また、簿記を学ぶことで財務諸表の読み方やお金の流れを理解し、数値をもとに論理的に判断する力も身に付きます。このスキルは、経理や財務に関する職種に限らず営業や企画、経営など幅広い業務で求められるため、学生のうちに取得しておくことで社会人としてのよいスタートを切れるでしょう。
なお、簿記1級以上になると難易度は高まり、税理士などのスペシャリストを目指す人向けの試験内容になります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 企業の経営活動を記録・計算・整理する技能を証明する資格 |
| 合格率や難易度 |
3級:約35%〜50% 2級:約15%〜40% ※ネット試験、統一試験によって合格率に変動あり |
| 試験実施時期 | 3級、2級は各地テストセンターで随時ネット受験可能で、統一試験は6月、11月、翌年2月に実施 |
| 受験にかかる費用 | 3級:3,300円 2級:5,500円 |
| 勉強時間の目安 | 3級:120時間〜140時間程度 2級:250時間〜350時間程度 |
⑤Microsoft Office Specialist(MOS)
Microsoft Office Specialist(MOS)は、多くの企業が導入・利用しているマイクロソフト社の製品の操作スキルを証明する資格です。資料作成やメール、チャットなどさまざまな機能を使いこなす操作スキルが身につき、課題のレポート作成や仕事を効率的に素早く進められるようになります。
また、合格すると世界共通のデジタル認定証が発行され、就職活動においても実践的なパソコンスキルがあると評価されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | マイクロソフト社が主催する試験で、Word、Excel、PowerPoint、Access、OutlookなどMicrosoft Office製品の操作スキルを評価・証明する資格 |
| 合格率や難易度 |
一般レベル:約80% 上級レベル:約60% |
| 試験実施時期 | 毎月第2月曜(月によって変動)、または全国の認定試験会場で随時実施 |
| 受験にかかる費用 | 学生割引価格で8,580円〜1万780円 ※受講する試験によって異なる |
| 勉強時間の目安 |
一般レベル:20時間〜80時間程度 上級レベル:40時間〜80時間程度 |
ExcelやPowerPointの基本的な使い方については、以下の講座と記事で解説しています。
実践的に学びたい人は、具体的な操作を身に付けられる講座がおすすめです。
まずは基本から学びたい人は、ポイントをわかりやすく解説している記事をご覧ください。
⑥FP技能検定(ファイナンシャルプランナー)
FP(ファイナンシャルプランナー)技能検定は、お金のプロフェッショナルとして貯蓄や投資など家計のアドバイスをおこなうために必要な知識を有することを証明する資格です。金融系職種を志望している人にとっては業務に直結する内容を学ぶことができます。
また、FPの勉強で身に付けた知識は日々の生活でも活用できます。例えば、自分に合った保険を選ぶ場合や、将来に向けた資産形成を考える場合などさまざまなシーンで役立ちます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 顧客の資産に応じた貯蓄や投資などのプランを立案し、アドバイスする能力を認定する資格 |
| 合格率や難易度 |
3級:約80%程度 2級:約50%程度 1級:20%以下 |
| 試験実施時期 |
3級:毎月1回程度 2級:5月、9月、翌年1月に実施 1級:9月に実施 ※3級、2級は学科・実技の2科目 ※1級は実技のみ |
| 受験にかかる費用 |
3級:8,000円 2級:1万1,700円 1級:2万円~2万8,000円 ※いずれも学科・実技試験の合計 |
| 勉強時間の目安 |
3級:80時間〜150時間程度 2級:150時間〜300時間程度 1級:450時間〜600時間程度 |
⑦秘書技能検定
秘書技能検定とは、社会人としてのマナーや必要とされる対人スキルを証明するための試験です。秘書という名称ですが、秘書業務以外にも役に立つ内容が多く含まれています。ビジネスシーンで顧客や上司、同僚、部下との接し方を勉強できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 社会に出て働くうえで備えておきたい基本的な常識が身に付いているかを評価する資格 |
| 合格率や難易度 |
3級:約70% 2級:約60% 準1級:約40% 1級:約30% |
| 試験実施時期 |
3級・2級:2月、6月、11月の年3回 準1級:6月、11月の年2回 1級:6月、11月の年2回 ※3級と2級は筆記試験のみ ※準1級と1級は筆記試験+面接 |
| 受験にかかる費用 |
3級:3,800円 2級:5,200円 準1級:6,500円 1級:7,800円 |
| 勉強時間の目安 |
3級:30時間程度 2級:50時間程度 準1級:100時間程度 1級:150時間程度 |
⑧普通自動車免許
普通自動車免許は、日本の公道で自動車を運転する際に必要な資格です。
公共交通機関が発達していない場所に就職する場合や顧客訪問先へのアクセスが良くない場合などでは、仕事で自動車を利用するケースもあるでしょう。職種によっては自動車免許の取得を必須としている場合もあるため、大学生のうちに取得しておくと就職先の幅を広げられます。
また実生活においても、趣味でドライブを楽しんだり、移動手段として活用できたりと多くのメリットがあります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 日本の公道で普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転をするために必要な資格 |
| 合格率や難易度 | 約80% |
| 試験実施時期 | 各都道府県の運転免許センターで随時実施 |
| 受験にかかる費用 | 3,800円 |
| 勉強時間の目安 |
学科教習26時限 技能教習34時限(MT)、31時限(AT) |
⑨教員免許
教員免許は、学校の先生を目指す人には必須の資格です。一般企業に就職するうえでもプラスの評価につながる可能性があり、進路の幅を広げられるでしょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 教員として必要な資質や能力があるかを評価する資格 |
| 合格率や難易度 | 教員採用試験の合格率は約35% |
| 試験実施時期 |
教員採用試験:各自治体がおこない、公立は年に1回、私立は各学校で実施 教員資格認定試験:文部科学省がおこない、毎年5月に一次試験・9月に二次試験を実施 |
| 受験にかかる費用 |
公立学校の教員採用試験:無料 教員資格認定試験:認定試験によって異なる 幼稚園教員で2万円 小学校教員で2万5,000円 高等学校教員で2万5,000円 特別支援学校教員で1万5,000円 |
| 勉強時間の目安 | 600時間~1,000時間程度 |
教員は、子どもたちの将来を支援するやりがいある仕事です。仕事内容に興味がある場合は以下の講座も受講してみましょう。
⑩宅地建物取引士
宅地建物取引士は、宅建とも呼ばれる不動産分野の資格です。
不動産業界での仕事に興味がある人にとっては、専門知識を身に付ける意味で効果的な資格となります。
宅地建物取引業を営む場合、1つの事務所につき従業員5人ごとに1人の割合で宅建士資格取得者の配置が義務づけられており、需要の高い資格です。
ただし、不動産取り扱いのプロフェッショナルとして専門知識が求められることから、難易度の高い資格でもあります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 不動産取引に関する専門家であることを認定する資格 |
| 合格率や難易度 | 15%~20%程度 |
| 試験実施時期 | 毎年10月の第3日曜日 |
| 受験にかかる費用 | 8,200円 |
| 勉強時間の目安 | 200時間〜500時間程度 |
⑪中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業に対する経営アドバイザリー業務をおこなうための専門知識を証明する資格です。将来コンサルタントとして活躍したい人はもちろん、ビジネスパーソンとして顧客をより深く知るための知識を身に付けたい人にも有効な資格です。
ただし、高い専門性が求められるため難易度は高く、計画的に勉強する必要があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 中小企業の経営に関するアドバイスをおこなう経営コンサルタントとして経済産業大臣が登録する資格 |
| 合格率や難易度 |
1次試験:約28% 2次試験:約19% ※1次、2次試験全体での合格率は4%前後 |
| 試験実施時期 |
1次試験:8月上旬 2次試験:10月下旬に筆記試験、翌年1月中旬に口述試験 |
| 受験にかかる費用 |
1次試験:1万4,500円 2次試験:1万7,800円 |
| 勉強時間の目安 | 800時間〜1,200時間程度 |
⑫公認会計士
公認会計士は、会計監査のプロフェッショナルとして高い難易度と知名度を誇る資格です。
資格取得者はコンサルタントとして企業のアドバイザーを務めたり、自社の会計部門を担ったりと幅広く活躍できる可能性があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 企業の会計や監査、経営に関する専門的な知識と技能を有することを証明する資格 |
| 合格率や難易度 | 10%以下 |
| 試験実施時期 |
第1回短答式試験:12月 第2回短答式試験:翌年5月 論文式試験:8月 |
| 受験にかかる費用 | 1万9,500円(短答式と論文式あわせて) |
| 勉強時間の目安 | 2,000時間~3,500時間程度 |
⑬弁理士
弁理士は、知的財産権を取り扱うプロフェッショナルとして、法律や製品に対する専門的な知識をもとに発明者の権利を守る役割を担います。中小企業診断士や公認会計士と同じく高難易度の資格のため、資格取得を目指す場合は大学1年生の時点から計画的に勉強スケジュールを組み立てる必要があるでしょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 知的財産権に関する専門家で、発明者の権利を保護する役割を担うための知識を証明する資格 |
| 合格率や難易度 | 6%〜9%程度 |
| 試験実施時期 |
短答式筆記試験:5月頃 論文式筆記試験:7月頃 口述試験:10月頃 |
| 受験にかかる費用 | 1万2,000円 |
| 勉強時間の目安 | 2,000時間〜3,000時間程度 |
⑭弁護士
弁護士は難易度が非常に高い資格の一つで、将来の就職先としては弁護士事務所や企業の法務担当、コンサルタント職種などが挙げられます。試験では、法律の知識を活用して依頼者の権利・利益をどう守るかを問う内容が出題されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 法律の専門家として依頼者の権利や利益を守り、社会正義を実現するための資格。法科大学院修了者もしくは予備試験合格者のみ司法試験の受験が可能 |
| 合格率や難易度 |
予備試験:3~4%程度 司法試験:20~40%程度 |
| 試験実施時期 |
予備試験:短答式が7月・論文式が9月・口述試験は翌年1月 司法試験:短答式・論文式ともに毎年7月 |
| 受験にかかる費用 |
予備試験:1万7,500円 司法試験:2万8,000円 |
| 勉強時間の目安 | 3,000時間〜8,000時間程度 |
⑮行政書士
行政書士は、顧客から依頼を受けて官公署への許認可申請に必要な書類の作成やアドバイスをおこなう法律の専門家です。
官公署などの行政を相手に手続きを進める際は専門的な知見が必要不可欠です。さらに、手続きが煩雑で時間がかかるケースも多く見られます。行政書士は専門的知見を活かしてその手続きを迅速かつ正確に進められるため、依頼者にも行政にも余計な手間をかけさせず、事務処理を効率化する役割を担っています。
就職先の企業で行政との手続きを担当する部署に配属される可能性もありますので、社会人になる前から専門知識を備えていることは大きなアドバンテージとなるでしょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 資格概要 | 官公署に提出する申請書類の作成や提出手続き、遺言書や契約書の作成、行政不服申立て手続きなどをおこなうための知識・技能を証明するための資格 |
| 合格率や難易度 | 10%前後 |
| 試験実施時期 | 毎年11月の第2日曜日 |
| 受験にかかる費用 | 1万400円 |
| 勉強時間の目安 | 500時間〜1,000時間程度 |
3.大学生が資格を取得するメリット

大学生が資格を取得するメリットは、就職活動でアピールできることだけではありません。自身の将来的なキャリアを形成するうえでプラスとなる面もあります。
①自己成長につながる
資格取得を通じて得た学びの多くは、社会人になってからも活用できます。
例えば、簿記の資格を取得しているなら、企業が開示した決算書を見て事業の状態や今後の成長可能性をより詳細に把握できるようになるでしょう。営業職であれば決算書の内容をベースにしたディスカッションができ、顧客からの信頼獲得につながるかもしれません。
また、資格を取得するための計画性や目標達成に向けて継続的に取り組む姿勢は、自己成長の機会となるでしょう。
計画力は社会人に求められる大切な能力です。計画力について、詳しく知りたい人や実践的に身に付けたい人はぜひ以下の講座をご覧ください。
②キャリアの選択肢が広がる
資格を取得することは、単に試験に合格した証明となるだけではなく、あなた自身のキャリアの選択肢を広げることにもつながります。
例えば、「教員」のように資格がなければ挑戦するのが難しい職種もあります。また、資格が必須でなくても、特定の資格を持っていることで選考で有利になったり、業務の幅が広がったりすることがあります。
そのため、興味のある資格を取得することが、結果的に自分に合ったキャリアを見つけるための第一歩となります。
③資格取得までの計画を立てやすい
社会人になってから資格を取得する人もいますが、なかには日々の仕事の合間に勉強を続けることが難しいと感じる人もいるでしょう。
その点、大学生は長期休暇や空きコマの時間などを使って集中的に勉強に取り組みやすく、資格取得までの計画が立てやすい環境にあります。自由に使える時間が多い大学生のうちに資格を取得することは大きなアドバンテージといえるでしょう。
以下の記事でも、さまざまな観点から将来に活きる大学生活の過ごし方をご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
④給料に資格手当が付く場合がある
資格を保有していることで、給料にプラスして資格手当が付与される場合があり、収入アップが実現する可能性があります。
例えば不動産会社に入社した場合、宅地建物取引士の資格を持っていると、1万円から3万円程度の手当が支給されるケースはよくあります。このように、大学生の間に取り組んだ勉強時間が先行投資となって、就職したあとに給与として戻ってくることもあるのです。
4.押さえておきたい!資格取得を目指す際のポイント

最後に、資格取得を目指すうえで押さえておきたいポイントをご紹介します。
①資格取得の目的を明確にする
まず、資格取得の目的を明確にします。なぜこの資格を取得したいのか、あなた自身にとってその資格を取得することにどのような意味があるのかを言語化してみましょう。
例えば、「将来やりたいことにつながるから」「実生活において役立つと思うから」など明確な目的を探してみてください。
②自分の興味関心を把握しておく
あなた自身が興味関心を持てる分野であれば、資格取得のための勉強もはかどるでしょう。その勉強で得た学びや気付きが就職活動のときに志望理由につながるかもしれません。特に、面接で「なぜその企業を志望するのか」を説明するときに、資格の勉強を通じて得た経験や学びを交えることで、より説得力のある志望動機を伝えられるでしょう。
興味関心のある分野がわからない場合は、まず自己分析から始めることをおすすめします。自分自身のこれまでを振り返り、どのようなときに楽しみややりがいを感じるのか、どのようなときにモチベーションが低くなってしまうのかなど、価値観や行動を見つめ直してみましょう。そして、自己分析を通じて見えてきた自分の価値観に対し、合致する資格はなにかを探してみることをおすすめします。
以下の講座では自己分析の実践的な方法をご紹介していますので、ぜひご覧ください。
自己分析のやり方や自己理解を深めるメリットは以下の記事でも解説しています。
③勉強時間の目安を知っておく
資格によって目安の勉強時間は大きく異なります。実際にどの程度の時間を確保することが可能かを明確にし、資格取得に向けて計画を立てましょう。
例えば、大学3年生の時点で資格取得の勉強を始めようと思っても、大学生として過ごす残り時間はそこまで多くないため、取得を目指せる資格は限られます。そのため、大学生として過ごす時間が多くある1年生のうちから資格取得のための時間を逆算するのがおすすめです。
④資格を取得する時期を見極める
資格取得の時期を見極めることも大切です。
就職活動を本格的に始める前に資格を取得しておけば、履歴書やエントリーシートに保有資格を記載できます。
なかには、部活動やゼミなどで忙しく、落ち着いてから資格の勉強を始めようと考えている人もいるでしょう。仮に就職活動後に資格の試験がある場合でも、試験勉強をしている旨を伝えられれば学びの意欲を十分アピールできます。
いずれにしても「定期テストのタイミングと重なっていて資格勉強の時間が取れなかった」といったことがないよう、計画的に資格取得のスケジュールを設計しましょう。
My CareerStudyでは、目標を達成するためのロードマップを作成できる「マイロードマップ」を用意しています。また、目標達成のためのタスク管理の方法については、以下の講座や記事でご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
5.まとめ
大学生は、時間割を比較的自由に組むことができたり、長期休暇があったりと、自己投資に費やせる時間が多くあります。この貴重な時間を有意義に過ごし、目的を持って取り組むためにも資格取得はおすすめです。
資格取得という目標達成のためには、計画性と継続力が必要です。これらのスキルは社会人になってからも有効なものですので、大学生のうちから意識していきましょう。
以下の講座では、取得した資格を就職活動の場面で効果的にアピールする方法をご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

執筆:My CareerStudy編集部
My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。
就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。