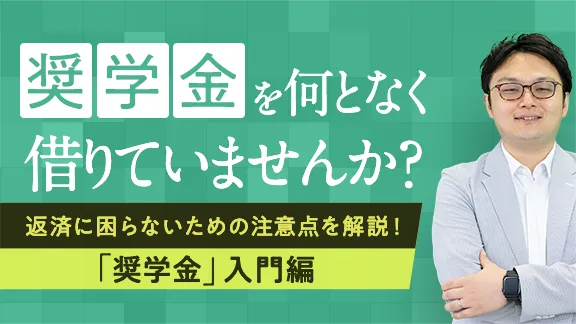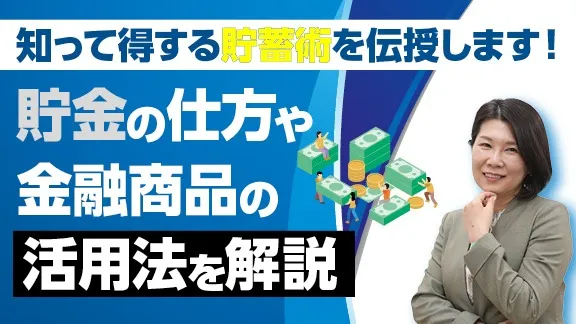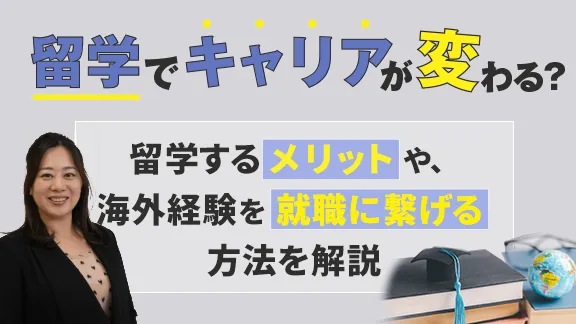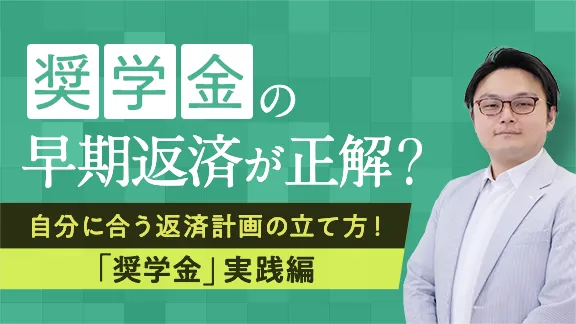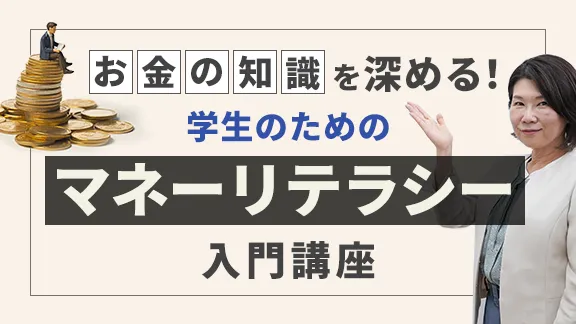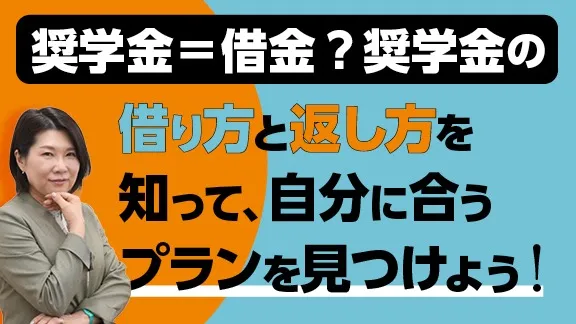奨学金とは?種類や申し込みの流れ、利用時の注意点を解説
- 公開日
- 2025/04/07
この記事は8分で読めます

家庭の事情や経済的な理由で、奨学金の利用を検討している人もいるでしょう。
ひとくちに奨学金といってもさまざまな種類があり、それぞれ対象者や採用基準が異なります。
この記事では、奨学金制度の概要や貸与型・給付型の違い、採用基準、受け取れる金額、利用時の注意点などを詳しく解説します。
奨学金の利用を検討している人は、ぜひ以下の講座も併せて参考にしてみてください。
My CareerStudyの動画講座ではアカウント登録をすることで誰でも無料で社会で役立つ知識やスキルを身につけることができます。
目次
1.奨学金制度とは?

奨学金制度は、家庭の事情や経済的な理由で大学などへの進学や学業の継続が難しい学生に対して学費の支援をおこなう制度のことです。学費や生活費など学生の経済的な負担を軽減することで、学生が勉学に専念できる環境を整え、将来の人材育成につなげることを目的として運営されています。
奨学金には大きく分けて貸与型と給付型があり、家庭の経済状況によって選択できる奨学金が異なります。家庭の収入が少ないほど支給額が優遇される仕組みです。
では、どれくらいの学生が奨学金を利用しているのでしょうか。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)のデータによると、奨学金を受給している人の割合は以下のとおりです。
| 年度 | 平成30年度 | 令和2年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 大学学部(昼間部) | 47.5% | 49.6% | 55.0% |
| 短期大学(昼間部) | 55.2% | 56.9% | 61.5% |
| 修士課程 | 48.0% | 49.5% | 51.0% |
| 博士課程 | 53.5% | 52.2% | 58.9% |
| 専門職学位課程 | 41.1% | 37.1% | 41.4% |
出典:独立行政法人 日本学生支援機構「令和4年度 学生生活調査結果」
奨学金は限られた人しか利用できないイメージがあるかもしれません。しかし実際には、学生のおよそ2人に1人が利用していることがわかります。
ここからは、奨学金制度を実施している団体や奨学金の対象者について見ていきましょう。
1-1 奨学金制度を実施する団体
奨学金の運営組織は、大きく以下の2種類に分かれます。
- 公的奨学金:国・地方公共団体などが運営する奨学金
- 民間奨学金:民間の育英団体や、大学などが独自に実施している奨学金
公的奨学金として多くの学生が利用しているのが、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。一方、民間の奨学金には、大学や育英団体、企業などが実施しているものがあり、その数は3,800以上にのぼるとされています。
1-2 奨学金の対象者
奨学金を借りられるのは学生本人です。また、高等学校・大学・大学院・短期大学・専門学校だけでなく、海外の学校や通信制の学校に進学する人や在学中の人も対象です。ただし、学生であれば誰でも利用できるわけではなく、団体が定める採用基準をクリアする必要があります。
2.「貸与型」と「給付型」の違い

前述したとおり、奨学金には大きく分けて貸与型と給付型があります。ここでは、特に利用者が多い日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を例に貸与型と給付型の違いをご紹介します。
それぞれの違いをまとめると以下のとおりです。
| 比較項目 | 貸与型奨学金(第一種・第二種) | 給付型奨学金 |
|---|---|---|
| 返還義務の有無 | あり | なし |
| 利子の有無 | ● 第一種:なし ● 第二種:あり |
なし |
| 採用基準 | 第一種のほうが第二種よりも採用基準が厳しい | 貸与型よりも採用基準が厳しい |
| 採用人数(令和5年度) | ● 第一種:約18万人 ● 第二種:約20万人 |
約12万人 |
出典:
独立行政法人
日本学生支援機構 「〔貸与奨学金〕新規採用者数(学校の所在地:令和5年度)」
独立行政法人
日本学生支援機構 「〔給付奨学金〕新規採用者数(学校の所在地:令和5年度)」
貸与型は将来的に返還の必要があり、無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」に分かれます。
給付型は、意欲と能力があるにもかかわらず経済的な理由から進学・修学が困難な学生向けの制度です。返還不要ですが、より厳しい学力基準と家計基準をクリアする必要があります。
3.奨学金の採用基準は?合否はどこで決まる?

奨学金の採用基準には学力基準(奨学金を利用するために満たす必要がある成績・能力の基準)と家計基準(奨学金の給付額に関係する、学生本人と生計維持者の収入の水準)の2つがあり、両方の基準を満たすことで奨学金を受け取れます。また、奨学金に申し込むタイミングによって進学前(予約採用)と進学後(在学採用)に分かれており、それぞれ基準が異なります。
ここからは、大学への進学を予定している人や在学中の人を対象とした、貸与型と給付型の採用基準について解説していきます。
3-1 貸与型の採用基準
貸与型の奨学金には無利子の第一種奨学金と有利子の第二種奨学金があり、第一種奨学金のほうがより厳しい条件が設定されています。
①第一種奨学金の採用基準
第一種奨学金の採用基準はそれぞれ以下のとおりです。
| 区分 | 学力基準 | 家計基準 |
|---|---|---|
| 予約採用 |
次の1または2のいずれか1つに該当すること 1. 高等学校などにおける申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上※1 2. 高等学校卒業程度認定試験合格者 |
● 第一種のみ:生計維持者の貸与額算定基準額※2が189,400円以下 ● 第二種との併用:生計維持者の貸与額算定基準額が164,600円以下 |
| 在学採用 |
※2024年度入学者の場合 以下の1~3のいずれかに該当すること 1. 高等学校または専修学校高等課程最終2ヵ年の成績の平均が3.5(専修学校(専門課程)の場合は3.2)以上 2. 高等学校卒業程度認定試験の合格者 3. 生計維持者※3の貸与額算定基準額が0円である、生活保護受給世帯である、社会的養護を必要とする者※4であって、以下のいずれかに該当すること ● 入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属する ● 学修計画書などを通じて、将来社会で自立し活躍することを目標とし、意欲を持って学修に取り組む姿勢が確認できる |
- ※1:学習意欲があり、一定の要件を満たす場合は基準に達していなくても貸与が認められるケースがある
- ※2:給与収入などの情報をもとにして算出される、奨学金の貸与額の基準となる金額のこと
- ※3:学生の学費や生活費を負担する人のことを指し、原則として父母が該当する
- ※4:児童養護施設などの入所者や里親による養育を受けている者など
出典:
独立行政法人
日本学生支援機構「進学前(予約採用)の第一種奨学金の学力基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「進学前(予約採用)の第一種奨学金の家計基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「進学後(在学採用)の第一種奨学金の学力基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「大学等で受ける第一種奨学金の家計基準(在学採用)」
②第二種奨学金
第二種奨学金の採用基準は以下のとおりです。
| 区分 | 学力基準 | 家計基準 |
|---|---|---|
| 予約採用 |
以下の1~4のいずれかに該当すること 1. 高等学校または専修学校(高等課程)における学業成績が平均水準以上 2. 特定の分野において特に優れた資質能力を有する 3. 進学先の学校での学修意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがある 4. 高等学校卒業程度認定試験合格者 |
● 第二種のみ:生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下 ● 第一種と併用:生計維持者の貸与額算定基準額が164,600円以下 |
| 在学採用 |
以下の1~4のいずれかに該当すること 1. 出身学校または在籍する学校の成績が平均水準以上 2. 特定の分野において特に優れた資質能力を有する 3. 学修意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがある 4. 高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められること |
出典:
独立行政法人
日本学生支援機構「進学前(予約採用)の第二種奨学金の学力基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「進学前(予約採用)の第二種奨学金の家計基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「進学後(在学採用)の第二種奨学金の学力基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「大学等で受ける第二種奨学金の家計基準(在学採用)」
3-2 給付型の採用基準
給付型の採用基準は、貸与型と比較して厳しくなっています。
予約採用、在学採用それぞれの採用基準は以下のとおりです。
| 区分 | 学力基準 | 家計基準 |
|---|---|---|
| 予約採用 |
以下の1~2のいずれかに該当すること 1. 高等学校などで第1学年から申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上 2. 文書や面談を通じて、将来社会で自立し活躍することを目標として進学先での学修意欲が確認できる |
▼収入基準 【第1区分】自身と生計維持者の市町村民税所得割が非課税 【第2区分】自身と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満 【第3区分】自身と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満 【第4区分】自身と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満 ▼資産基準 申込日時点の自身と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満) |
| 在学採用 |
【1年次】次の1~3のいずれかに該当すること(秋入学者も含む) 1. 高等学校などにおける評定平均値が3.5以上、または、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属する 2. 高等学校卒業程度認定試験の合格者 3. 学修計画書などを通じて、将来社会で自立し活躍することを目標とし、意欲を持って学修に取り組む姿勢が確認できる |
出典:
独立行政法人
日本学生支援機構「進学前(予約採用)の給付奨学金の学力基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「進学後(在学採用)の給付奨学金の学力基準」
独立行政法人
日本学生支援機構「進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準」
各奨学金の詳しい採用条件については、学校の奨学金窓口や日本学生支援機構に相談することをおすすめします。
以下の講座では、奨学金について詳しく解説しています。ぜひ受講してみてください。
4.奨学金はどれくらい受け取れる?

奨学金として受け取れる金額は、奨学金の種類によって異なります。貸与型・給付型でそれぞれ受給できる金額は以下のとおりです。
4-1 貸与型の貸与額
貸与型の貸与額は、第一種奨学金、第二種奨学金、入学時特別増額貸与奨学金で異なります。
第一種奨学金では、国公立・私立といった学校の種類や、通学形態(自宅通学・自宅外通学)によって選択できる貸与額が以下のように変動します。
| 区分 | 貸与額 | |
|---|---|---|
| 国公立 | 自宅 |
● 20,000円 ● 30,000円 ● 45,000円 |
| 自宅外 |
● 20,000円 ● 30,000円 ● 40,000円 ● 51,000円 |
|
| 私立 | 自宅 |
● 20,000円 ● 30,000円 ● 40,000円 ● 54,000円 |
| 自宅外 |
● 20,000円 ● 30,000円 ● 40,000円 ● 50,000円 ● 64,000円 |
出典:独立行政法人 日本学生支援機構「平成30年度以降入学者の貸与月額」
第二種奨学金では、通学の環境に関係なく、20,000円~120,000円から1万円単位で月額を選択できます。なお、私立大学(薬・獣医学課程)の場合は月20,000円、私立大学(医・歯学課程)の場合は月40,000円まで増額できます。
出典:独立行政法人 日本学生支援機構「第二種奨学金の貸与月額」
第一種奨学金や第二種奨学金とは別に入学する月に「入学時特別増額貸与奨学金」を利用する場合、次の中から選択した金額が増額される形で貸与されます。
- 100,000円
- 200,000円
- 300,000円
- 400,000円
- 500,000円
4-2 給付型の給付額
給付型の給付額は第1区分から第4区分まで分かれており、給付額は以下のとおり異なります。また、国公立・私立といった学校の種類や、通学形態(自宅通学・自宅外通学)によっても給付額が変動します。
| 区分 | 自宅 | 自宅外 | |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 第1区分 | 29,200円 | 66,700円 |
| 第2区分 | 19,500円 | 44,500円 | |
| 第3区分 | 9,800円 | 22,300円 | |
| 第4区分 | 7,300円 | 16,700円 | |
| 私立 | 第1区分 | 38,300円 | 75,800円 |
| 第2区分 | 25,600円 | 50,600円 | |
| 第3区分 | 12,800円 | 25,300円 | |
| 第4区分 | 9,600円 | 19,000円 |
5.奨学金はどれくらい受け取れる?

奨学金には、入学前に申し込む予約採用と入学後に申し込む在学採用があり、それぞれで手続きの方法が異なります。ここでは、2つのうち多くの人が利用する予約採用の流れを日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を例に解説します。
STEP1:申し込みに必要な書類を集める
まず、申し込みに必要な書類を集めましょう。提出先は、日本学生支援機構(JASSO)と在学中の学校に分かれます。
| 提出先 | 必要書類 | 提出が必要な人 |
|---|---|---|
| 日本学生支援機構 | マイナンバー提出書 | 全員 |
| 番号確認書類 | ||
| 身元確認書類 | ||
| 学校 | 提出書類一覧表 | |
| 給付奨学金確認書 | 給付型奨学金を希望する人 | |
| 貸与奨学金確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 | 貸与型奨学金を希望する人 | |
| 在留資格の証明書類 | 申込者の国籍が日本国以外の場合 | |
| 施設等の在籍証明書等 | 社会的養護を必要とする人 | |
| マイナンバー代用書類提出台紙、マイナンバー代用書類 | マイナンバーや番号確認書類を提出できない人 | |
| 年収等の実績計算書、収入証明書等 | 1月1日時点で海外居住をしていた申込者や生計維持者がいる世帯 | |
| 海外居住者のための収入等申告書 |
出典: 独立行政法人 日本学生支援機構「予約採用申込みの手引き(奨学金案内)
奨学金の関係書類は、進学前に在学している学校で受け取ることができます。
STEP2:学校を通じて申し込みをおこなう
必要書類が揃ったあとは、在学中の学校を通じて申し込み手続きをおこないます。まず学校から、日本学生支援機構(JASSO)のインターネット情報システムであるスカラネットの申し込みに必要なユーザーIDとパスワードを受け取り、学校が定める期限までに申し込みをおこないます。
また、JASSOへのマイナンバーの提出、学校への必要書類の提出も同時に進めます。必要な書類が多いため、提出する際は不足や記入ミスがないよう注意しましょう。
STEP3:採用候補者の決定通知を受け取る
奨学金の選考が終わると、「採用候補者に選考結果」が通知されます。
採用候補者の決定通知は奨学金の候補者として選ばれたことを示す書類で、申込・推薦期限の約2ヵ月後に学校へ通知されます。
採用候補者の決定通知には「採用候補者のしおり」が同封されており、今後はその内容に従って奨学金の振込口座や進学先に提出する書類などの準備を進めることになります。
STEP4:進学後に正式な受給手続きをおこなう
進学後、進学先の学校で採用候補者決定通知【進学先提出用】を提出し、「進学届入力下書き用紙」と「識別番号(ユーザーIDとパスワード)」を受け取ります。そして、学校が指定する時期までにスカラネットから進学届を提出します。
STEP5:奨学金の受給が始まる
ここまでの手続きを完了すると、正式に奨学金の受給が始まります。
大学に進学届などの必要書類を不備なく提出した場合、提出月からおおむね1~2ヵ月後に初回の奨学金が振り込まれます。
また、毎年1回、奨学金を継続するための手続きが必要になります。
具体的には、貸与型は「貸与奨学金継続願」の入力、給付型は「在籍報告」と家族情報などの入力が必要です。定められた期限までに忘れずにおこないましょう。
6.奨学金で失敗しないために知っておきたい注意点

奨学金を利用することで学費の負担が軽減され、家庭の事情や経済的な問題を抱えた学生でも勉強に集中できるようになります。しかし、利用するうえで知っておくべき注意点もあります。奨学金に申し込む前に、ここでご紹介する注意点を事前に把握しておきましょう。
6-1 貸与型には返還義務がある
給付型を利用する場合は返還する義務はありませんが、貸与型を利用する場合は卒業後に返還する必要があります。具体的には、貸与が終了した月の翌月から数えて7ヵ月目から引き落としが始まります。
奨学金の返還方法は、大きく分けて以下の2つです。
- 所得連動返還方式:所得によって毎月の返還額が決まる返還方式
- 定額返還方式:貸与額に応じて月々の返還額が算出され、返還期間内は毎月一定額を返還する方式
毎月の返還額は、借り入れた金額、選択した返還方法などによって異なります。確実に返還を続けるためにも、毎月どのくらいの返還が必要になるか、以下のようなツールでシミュレーションすることをおすすめします。
6-2 入学前の費用は奨学金で充当できない
奨学金が初めて振り込まれるのは入学後であり、初年度納付金など入学前に支払う費用は奨学金で充当することができません。そのため、事前に親に立て替えてもらったり、自分で貯金したりして、支払いに備えなければいけません。
貯金のコツは以下の記事と講座で詳しく解説しています。入学前の支払いに備えて貯金を考えている方は、ぜひご覧ください。
6-3 採用後も学業をおろそかにしない
奨学金の採用後は、定期的に成績・学習状況・生活状況などが確認されます。成績不振や単位不足などが原因で留年した場合は、奨学金の継続ができず、学費が支払えなくなる恐れがあります。
学費が支払えないと、返還が必要な奨学金を抱えたまま退学しなければならないこともあり得ます。
主体性について、詳しく学びたい人は以下の講座をご覧ください。
7.奨学金に関するよくある質問

最後に、奨学金に関してよくある質問と回答をピックアップしました。
7-1 奨学金の用途に制限はある?
奨学金の使い道は規定が設けられていないケースが多く、学業に関係する出費以外の支払いにも利用できます。例えば、食費や資格取得、就職活動の費用としても利用できます。
ただし、学業とは関係ない遊びやレジャーに奨学金を利用するのは避けましょう。一部の奨学金では、どの支払いに使用したか証明書の提出が求められるケースもあります。
7-2 留学向けの奨学金はある?
留学向けの奨学金もあります。
例えば、日本学生支援機構(JASSO)では、海外留学のための貸与型奨学金と給付型奨学金を提供しています。返還不要の給付型は、協定派遣、学部学位取得型、大学院学位取得型に分かれており、それぞれ支援する対象者が異なります。
給付型奨学金の種類と対象者の違いをまとめると以下のとおりです。
| 協定派遣 | 学部学位取得型 | 大学院学位取得型 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 日本の大学などが諸外国の学校と締結した学生交流協定に基づき、所定のプログラムに参加する日本人学生を支援する制度 | 学士の学位取得を目指して海外の大学に留学する人向けの制度 | 修士または博士の学位取得を目指して海外の大学に留学する人向けの制度 |
| 対象者 | 日本の大学などに在籍したまま、8日以上1年以内のプログラムに参加する学生 | 応募時に日本に在住していて、高等学校卒業後に海外にある大学で「学士号」の取得課程に直接進学する人 |
● 修士号または博士号の学位取得を目指して海外の大学院へ留学する人 ● 学士以上の学位をすでに取得した人、または取得予定の人 |
| 支援内容 | ● 給付額:月額60,000~100,000円 ● 渡航支援金:一定の家計基準を満たす場合は160,000円、一定の派遣期間を満たす場合は130,000円 |
● 給付額:月額124,000円~326,000円 ● 渡航支援金:支援開始時に160,000円 |
● 給付額:月額154,000円~356,000円 ● 渡航支援金:支援開始時に160,000円 |
| 支援期間 | プログラムによって異なる | 原則4年 |
● 修士の学位取得コース:2年 ● 博士の学位取得コース:原則3年 |
出典:
独立行政法人 日本学生支援機構「海外留学のための給付奨学金(返済不要)」
独立行政法人 日本学生支援機構「海外留学のための貸与奨学金(返済必要)」
以下の記事や講座では留学についてより詳しく解説しています。留学に興味のある人はぜひご覧ください。
7-3 奨学金を返還できないとどうなる?
奨学金の返還を延滞した場合、通常の利息に加えて遅延損害金が発生します。また、滞納が続くと個人信用情報機関(ローンや奨学金などの金融商品の取引記録である「信用情報」の収集・管理・開示などをおこなう機関)に情報が記録され、その後のローン契約やスマートフォンの割賦契約が難しくなるので注意が必要です。
もし卒業後にケガや病気、災害などで働くことができなくなった場合は、奨学金の運営元に月々の返還額の減額や返還期限を相談してみましょう。
奨学金が返還できなくなる事態を防ぐためには、将来を見据えて奨学金を借りる前から返還計画を立てておくことが重要です。以下の講座では、奨学金の返還計画の立て方について分かりやすく解説しています。奨学金の返還に不安を感じている人はぜひご覧ください。
8.まとめ
奨学金を利用すれば、経済的な理由で進学が難しい人でも学業に励めるようになります。
ただし、ひとくちに奨学金といっても、制度内容や対象者、貸与額・給付額などは団体によって異なり、将来の返還額も変動します。返還が必要な貸与型を選択する場合、将来的に返還できなくなる事態を避けるためにも綿密な返還計画を立てるようにしましょう。
My CareerStudyでは、奨学金について基礎から学べる講座をご用意しています。奨学金の利用をお考えの人はぜひご覧ください。

執筆:My CareerStudy編集部
My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。
就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。