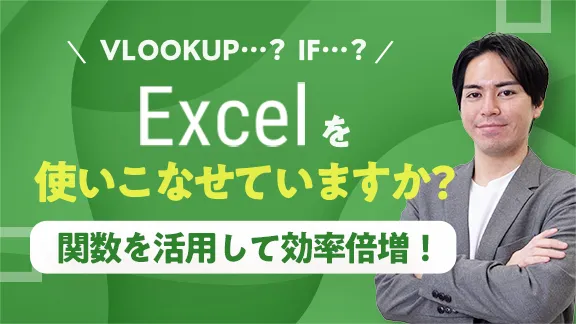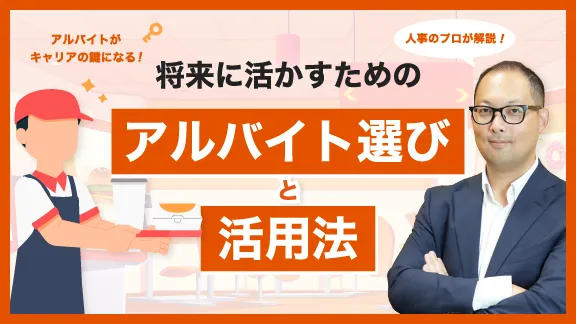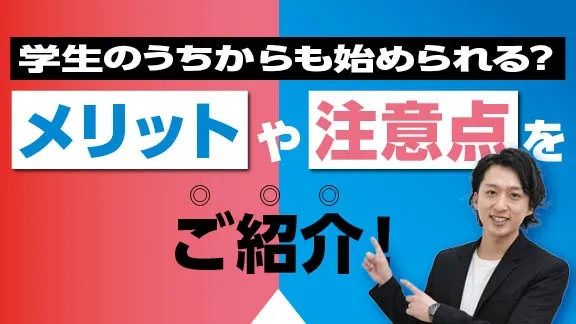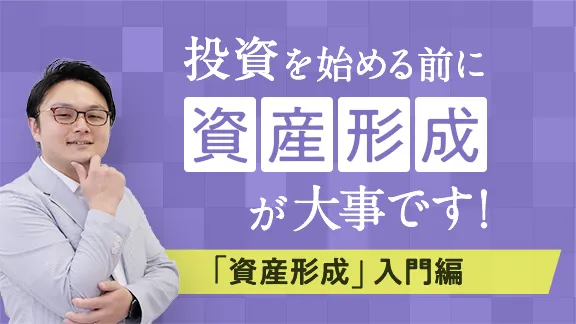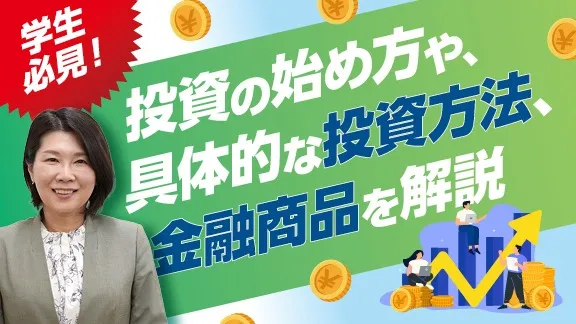大学生の平均貯金額は?貯金のコツや効率的に増やす方法をご紹介
- 公開日
- 2025/02/10
この記事は7分で読めます

大学生になると自由な時間が増える一方、やりたいことやできることが広がり、サークル活動や就職活動などでお金が必要になる場面も増えます。また、将来のことを考えると今のうちからお金を貯めるべきではないかと考える人もいます。
そうしたお金をどのように貯めればよいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、大学生の貯金事情や貯めたお金の使い道、お金を貯めるために知っておきたい収支管理の方法、貯金のコツなどを解説します。
My CareerStudyの動画講座ではアカウント登録をすることで誰でも無料で社会で役立つ知識やスキルを身につけることができます。
1.調査結果から見る、大学生の貯金事情

まずは、大学生で貯金をしている人は何割ぐらいいるのか、平均でどのくらいの金額を貯金しているのか、調査データをもとに解説します。
①貯金をしている大学生はどれくらい?
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が実施したアンケート調査「10代の金銭感覚についての意識調査2024」によると、貯金をしている大学生・短大生・専門学校生・予備校生は57.5%です。一方、「貯金をしていないが、したいと思う」は33.5%、「貯金をしていないし、したいと思わない」は9%となっています。
貯金ができていない人は遊びも含めてお金を使いすぎてしまい、月末にお金が残っていないというケースも多いのではないでしょうか。
しかし過半数の学生が貯金できていることを考えれば、ちょっとした工夫で貯金することが可能でしょう。社会人になってからの出費や万が一の入院・通院などに備えるためにも、学生のうちに貯金する癖をつけておくことが大切です。
②大学生の平均貯金額は?
全国大学生活協同組合連合会が発表した「第59回学生生活実態調査(2023年10〜11月実施)」によると、自宅学生・下宿生の平均貯金額は以下のとおりです。 .5%です。一方、「貯金をしていないが、したいと思う」は33.5%、「貯金をしていないし、したいと思わない」は9%となっています。
| 学生の種類 | 毎月の平均的な貯金額 |
|---|---|
| 自宅学生 | 18,410円 |
| 下宿学生 | 14,740円 |
出典:全国大学生活協同組合連合会「第59回学生生活実態調査 概要報告」
この結果を踏まえると、大学生活4年間で自宅学生は88万3,680円、下宿学生は70万7,520円貯金できる計算です。なお同調査では、下宿学生は月に約7万円の仕送りを受け取っていることから毎月の貯金額は自宅学生と大きく変わらない結果となっています。
2.大学生の貯金の使い道

次に、大学生は貯めた貯金をどのような用途に利用しているのか具体例をご紹介します。
①欲しいものや趣味に使う費用
まずは、欲しいものや趣味のための出費が考えられます。
パソコンやスマートフォンなどの高額な電子機器、一人暮らしで利用する洗濯機や冷蔵庫などの家電、ライブやサッカー観戦など趣味への出費が考えられます。
②サークルや部活動の活動費用
サークル活動や部活動にも費用がかかります。前述した全国大学生協連の調査によれば、2023年4月〜9月の合宿費用の平均は4万5,500円です。
もし合宿が夏休みと冬休みの年2回あるとすれば、年間で約9万円の費用が発生する計算となります。
③旅行や遊びなどの娯楽費用
大学生になると行動範囲が広がり、国内旅行や海外旅行をする人も多いでしょう。
全国大学生協連の調査によると、2023年4月~9月の大学生の国内旅行の平均支出額は6万9,600円、海外旅行の平均支出額は20万4,500円となっています。
また、旅行以外でも友達と遊びに行くためには交通費や食事のための費用などがかかります。
大学生の平均アルバイト収入は自宅生で月4万3,010円、下宿生で3万6,110円であり、仮に自由に使えるお金をアルバイト収入に限定するとなると、海外はもちろん国内旅行に行くためにも貯金は必須といえます。
④留学へ行くための費用
英語力の向上を狙って語学留学を志す大学生もいるでしょう。
全国大学生協連の調査によれば、2023年の4月~9月の留学費用の平均額は52万7,900円となっています。
また、下記のとおり留学費用は年々増加傾向にあります。
| 年 | 平均費用 |
|---|---|
| 2019年 | 327,800円 |
| 2020年 | 323,100円 |
| 2021年 | 112,800円 |
| 2022年 | 450,600円 |
| 2023年 | 527,900円 |
2021年は新型コロナウイルスによる移動制限があったためあまり参考にはなりませんが、5年で約20万円も増加していることになります。
原因としては、近年の円安、原油や物価の高騰による航空機のチケット代、留学先の下宿費用の増加が考えられます。今後はさらなる上昇も考えられるため、留学を検討している場合は計画的な貯金が必要でしょう。
ただし、学校によっては留学奨学金制度を設けているところもあるため、自己負担する費用を抑えられる可能性もあります。まずは、大学のホームページでどのような支援制度があるのか調べてみましょう。
留学のメリットやキャリアへの活かし方などについて詳しく知りたい人は、以下のMy CareerStudyの講座もぜひ併せてご覧ください。
⑤勉強にかかる費用
大学に通うためには学費がかかります。選択した講義によっては指定された教材を購入しなければいけないケースもあるでしょう。
また、資格の取得にも費用がかかります。例えば、自動車運転免許を取ろうとした場合、免許合宿や教習所に通うための費用に加えて試験を受けるための費用も用意しなくてはなりません。
全国大学生協連の調査によると、2023年4月から9月までの運転免許取得費用は平均で27万1,800円、運転免許以外のスクールの費用は平均9万5,900円でした。スクールの種類によってはさらに高額な費用が発生する可能性もあるでしょう。
⑥将来の生活のための費用
大学を卒業して社会人として働き始めたときのことを考えて貯金をする学生もいます。
例えば、将来の結婚や出産などのイベントに向けて貯金を始める学生もいるでしょう。マイナビウエディングの調査によれば、結婚式の平均費用は320万5,000円でした。
ただし、親からの援助額は平均180万7,000円のため、実際の出費は約140万円弱が平均となります。しかし、ご祝儀である程度回収できるとしても残りの費用を自分で用意するためには計画的な貯金が欠かせません。
結婚するタイミングにもよりますが、若いうちに結婚を考えているなら学生時代から貯金をしておく必要があるでしょう。
出典:マイナビウエディング「【最新】結婚式の平均費用は? 内訳やご祝儀相場からみる自己負担額など、リアルな声をもとに徹底解説」
他にも、老後のために本格的に貯金を始める学生もいます。
2019年6月に金融庁の金融審議会が、「平均的な高齢夫婦世帯の場合、老後30年間で約2,000万円が不足する可能性がある」と試算した「老後2,000万円問題」が世間で議論を巻き起こしたこともあり、人によっては老後資金が不足するかもしれません。
仮に20歳から65歳までの間に老後の2,000万円を貯める場合、毎月約37,038円の貯金が必要になる計算です。
老後に必要な資金は環境や家庭ごとに異なるため、必ず2,000万円が必要ということではありませんが、不安がある場合は若いうちから少しずつ貯める必要があるでしょう。
⑦急な出費への備え
学生生活を送るなかで急な出費が発生することもあります。
例えば、通学中に思わぬ事故に巻き込まれたり、風邪が悪化して入院したりすることもあるかもしれません。
日本は国民皆保険制度を採用しており、学生でも医療費の3割を自己負担することで診療を受けられますが、自己負担分は用意しなければなりません。また、全額自己負担となる自由診療や先進医療を受ける場合には、十分な貯金が必要となるでしょう。
3.お金を貯めたいならまずは「収支管理」から

お金を貯める際の基本は、収入が支出を上回るよう「収支管理」をすることです。
ここでは、収支管理の進め方を3つのステップに分けて解説します。
STEP1:貯金の目的と目標金額を決める
お金を貯めるためには、まず貯金の目的を明確にすることが重要です。
目的とお金を貯める期限さえ決まれば、そこから逆算して毎月いくら貯金すべきかがわかります。
例えば卒業旅行を2年後に控えており、旅行代金を30万円と見積もっている場合、1ヵ月あたり1万2,500円を貯金する必要があります。目標を定めて「毎月いくら貯金に回す」という具体的な行動に落としこむことができれば、何をどうすればよいかわからない漠然とした状態から脱する大きな一歩となります。
STEP2:固定費と変動費に分けて収支を把握する
目的と目標が決まったら、毎月その金額を貯金できるように収支を見直します。
まずは自分が毎月いくら使っているのか、アルバイトやお小遣い、仕送りなどでいくらの収入を得ているかを明確にしましょう。
支出を見直す際は固定費と変動費に分類することが大切です。固定費は毎月ほぼ同じような金額が発生する支出のことを指し、変動費は月ごとに金額が変わり、予測が難しい支出のことです。
家計簿の項目を固定費と変動費に分けると、以下のとおりです。
| 固定費の例 | 変動費の例 |
|---|---|
|
|
STEP3:削減できる支出がないか検討する
貯金をする方法は、貯金したい分だけ収入を増やすか、貯金したい分だけ支出を減らすかのどちらかです。大学生の場合は学業を優先する以上、働く時間を増やすことは難しい人も多いため減らせる支出がないか見直すことを優先して考えましょう。
支出を見直す際は固定費を優先して見直すのがおすすめです。毎月一定額の支出が発生する固定費を見直せれば、継続的に節約できることになります。
STEP4:家計簿をつけて定期的に振り返る
目標となる貯金額が決まり、毎月の固定費や変動費を見直して貯金計画を立てたら、家計簿をつけて支出を定期的に振り返りましょう。
家計簿をつけることでお金の流れが明確になり、無駄な出費を把握できれば対策を考えやすくなります。家計簿をつけるには家計簿アプリを活用するほか、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ツールを使う方法もあります。
- 複数のデータをカテゴリごとにグループ化したい
- 複数のデータセットを1つのデータに結合したい
- 平均値や中央値などの基本統計を計算したい
Excelの使い方については、My CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。
また、以下の記事でもExcelの基本的な使い方をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
4.今日から実践できる!貯金のコツ

最後に、今日からすぐに実践できる貯金のコツをご紹介します。収支管理と併せて実践してみてください。
①銀行口座を使い分ける
1つ目のコツは、銀行口座を使い分けることです。
生活費を支払うための口座と貯金専用の口座に分け、貯金用の口座に入れたお金に手を出さないルールにすれば確実に貯金できるようになります。
貯金専用の口座に毎月決まった金額を確実に入金できるよう、先取り貯金も取り入れましょう。先取り貯金は、給料や仕送りなどが入ったときに目標の貯金額を先に貯金専用の口座に入金することです。そのうえで、残ったお金で毎月の生活費用を賄えば自然と節約できます。
②学割を有効活用する
学割の有効活用も貯金の成功につながります。
学割は映画や電車、書籍などさまざまな商品や施設で提供されており、1回数百円程度の節約になります。1回ごとの割引額は大きくなくても、何度も利用しているうちに数千円単位の節約になるため結果的に貯金につながります。
学割など大学生が利用できる制度や、大学生のうちにやるべきことについて詳しく知りたい人は、My CareerStudyの以下の記事も併せてご覧ください。
③ポイント還元を活用する
支払い方法を現金からクレジットカードや電子マネーに切り替えることでも節約につながります。
クレジットカードや電子マネーで支払うと、サービスによっては利用額の0.5%~1.0%程度のポイントが還元される場合があります。学生限定でお得なサービスを提供しているクレジットカードもあるため、上手に活用すればまとまったポイントを獲得できるかもしれません。
④収入を増やす
節約だけで目標の貯金額を達成するのが難しい場合は、収入を増やすことも検討しましょう。具体的な方法は以下の3つです。
1.アルバイトをする
もしアルバイトをしていないなら、アルバイトで収入を増やすことを検討しましょう。
例えば、節約だけでは目標の貯金額に月2万円届かない場合、時給1,000円のアルバイトで月20時間ほど働けば不足分が賄えることになります。
学生でも始めやすいアルバイトの例としては以下のようなものがあります。
- コンビニ
- 居酒屋
- ガソリンスタンド
- レストラン
- 引越し
- イベントスタッフ
- 塾講師 など
一方で、すでにアルバイトをしている人は学業に影響が出ない範囲でアルバイトの日数を増やすのもよいでしょう。
ただし、短時間で効率的に稼ぎたいからといってあまりにも高時給の怪しいアルバイトやマルチ商法のようなアルバイトに応募しないよう注意してください。
アルバイトの選び方についてはMy CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。
2.インターンシップ・仕事体験に参加する
就職活動が本格化する前の学生なら、インターンシップ・仕事体験に参加して収入を得ることもできます。
インターンシップ・仕事体験は短期のプログラムと長期のプログラムに分かれます。そのうち、長期のインターンシップ・仕事体験であればアルバイトと同様に給料がもらえるケースがあります。給与体系は時給・日給などのパターンがあり、金額はインターンシップ・仕事体験を開催する企業によって異なります。
また、インターンシップ・仕事体験は企業のオフィスで社員と働くことになります。正社員としての業務を体験すれば、将来の就職先を考えるきっかけにもなるでしょう。
インターンシップ・仕事体験については、My CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。
3.副業を始める
アルバイトとは別に空いた時間で取り組める副業を始めるのも手です。副業を探すには、求人サイトで別のアルバイトを探すほか、インターネットのクラウドソーシングサイトを利用するとよいでしょう。
クラウドソーシングとは、仕事の依頼側と受注側をマッチングするサービスのことです。
仕事内容は、データ入力やアンケートなど誰でもできる簡単なものから、Webライティングによる記事作成、動画編集、サムネイル画像のデザインなど知識やスキルが活かせるものまでさまざまです。このような副業であれば、自宅に居ながら空いた時間を有効に活用できる可能性があります。
副業については、My CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。
4.資産運用をする
資産運用とは通常の貯金と異なり、お金を使って株式や債券、投資信託などの金融商品を購入(投資)することです。
日本の主要銀行の普通預金の金利は2024年12月現在で年0.1%であり、銀行に預けていてもお金が増えづらくなっています。仮に100万円を普通預金口座に金利年0.1%で預けたとしても、1年後に受け取れる利子の額は税引き前で1,000円、税引き後は797円しか受け取れません。
| 普通預金の預入金額 | 1年後に受け取れる利子(金利年0.1%) | |
|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | |
| 10万円 | 100円 | 80円 |
| 50万円 | 500円 | 399円 |
| 100万円 | 1,000円 | 797円 |
また、2024年現在の日本はインフレの傾向にあり、2024年11月の消費者物価指数(2020年基準)は前年同月比2.9%プラスと上昇しています。
出典:総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国2024年(令和6年)11月分」
こうした状況から、預貯金だけでは資産が目減りする可能性があります。リスクもありますが、預貯金の一部を資産運用に割り振れば、預貯金以上のリターンが期待できるでしょう。
ただし、大学生が資産運用に力をすぎると、以下のようなデメリットが生じることもあるため注意が必要です。
- 日々の値動きが気になって学業や生活に影響する
- 元本割れを起こすリスクがある
投資対象によって値動きは異なり、売買はタイミングを見極める必要もあります。株価を定期的にチェックすることに気を取られ、大学の成績が悪化しては本末転倒です。
学業と資産運用を並行するなら、一度だけ積立の設定をすれば毎月一定額を口座に自動的に投資できる積立型の投資信託がおすすめです。しかし、株式も投資信託も元本保証(投資したお金が減らないことを保証する)がなく、運用結果次第では元本を割ってしまうかもしれません。興味がある人は、日常生活や学業に影響がない範囲で投資を始めましょう。
資産形成の基本については、My CareerStudyの以下の講座で詳しく解説しています。
5.まとめ
大学生の平均貯金額は1年で約17万円〜20万円程度です。一方、貯金の有無には同じ大学生の間でも個人差があり、なかにはほとんど貯金できていない学生もいます。
学生生活の後半では就職活動や卒業旅行などのイベントが多く、早いうちから貯金に取り組むことが大切です。
今回ご紹介した収支管理の基本や貯金のコツを実践し、卒業までの4年間で数十万円単位の貯金ができるように、無駄遣いを抑えて毎月の収支を黒字化する対策を考えていきましょう。
My CareerStudyでは、学生のうちに身に付けておきたいお金の知識をわかりやすく動画講座で解説しています。ぜひご覧ください。

執筆:My CareerStudy編集部
My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。
就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。