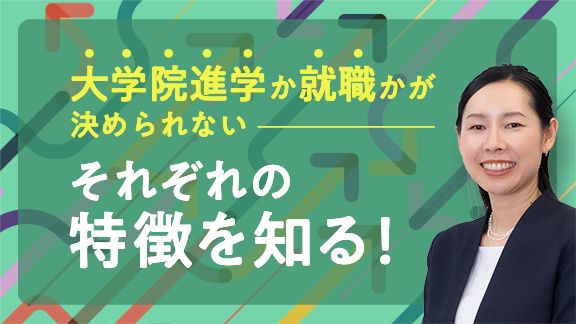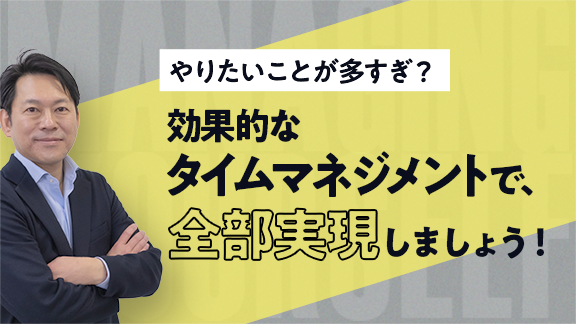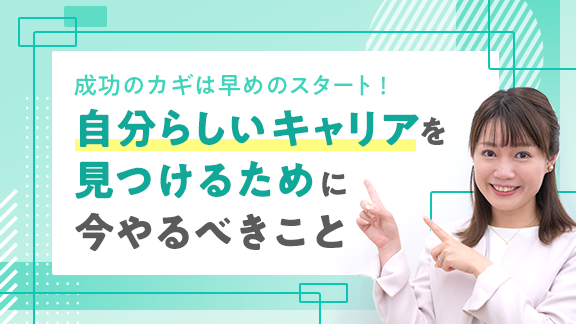大学院進学と就職で悩んだら?メリットとデメリット、進路選択のポイントを紹介
- 公開日
- 2024/2/29
この記事は8分で読めます

大学院へ進学するか就職するかでお悩みの人は多いのではないでしょうか。
大学院へ進学すると専門的な知識を活かした職種に就職できる可能性が高まります。一方で、就職するといち早く社会人としての実務経験が積めます。
それぞれにメリットがあるため、理想とするキャリアから逆算してどちらを選択すべきか考えてみましょう。
この記事では、大学院進学と就職のそれぞれのメリット・デメリット、進路選択でおさえておきたいポイントを解説します。
目次
1.大学卒業後の進路は大学院進学?就職?

まずは、文部科学省が公表している資料をもとに、大学院への進学率・就職率それぞれの割合を見てみましょう。
| 区分 | 進学率(%) | 就職率(%) | その他(%) |
|---|---|---|---|
| 令和2年3月 | 11.3 | 77.7 | 11.0 |
| 令和3年3月 | 11.8 | 74.2 | 14.0 |
| 令和4年3月 | 12.4 | 74.5 | 13.1 |
| 令和5年3月 | 12.5 | 75.9 | 11.6 |
大学院への進学率は微増していますが、ほとんどの学生は大学卒業後の進路として就職を選択していることがわかります。
2.そもそも大学院はどういうところ?

大学院は以下の4種類に分類されます。
| 大学院の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 各学部の大学院 |
●学部組織の上級機関として定義される
●学士課程での学びを活かしながらより専門性の高い研究をおこなう場 ●理系学部に所属する多くの学生が進学する |
| 独立研究科 |
●学部組織を持たない
●大学院だけで構成される独立機関として定義される ●さまざまな大学・学部出身の学生を受け入れ、個々の学びを合わせることで独自の研究をおこなう |
| 専門職大学院 |
●高い専門性を養うための機関として定義される
●教員を養成する教職大学院、法律のプロフェッショナルを養成する法科大学院などが例として挙げられる |
| 大学院大学 |
●学部組織では取り扱わない内容を研究する機関として定義される
●独立研究科と定義は似ている ●学部で学んでいないテーマが研究対象となる場合が多い |
出典: 文部科学省「大学院の目的・役割」
また、昨今では学校教育を経て社会人になってから、必要なスキルを身につけるために再度学び直す「リカレント教育」に対応している大学院も増えてきています。
3.大学院進学のメリット

続いて、大学院に進学することのメリットをご紹介します。
3-1 専門職につきやすくなる
1つ目のメリットは、専門職につきやすくなることです。
例えば将来的に教員を志望している場合は、大学院で所定の単位を修得すれば教員専修免許状が取得でき、法科大学院課程を修了すれば司法試験の受験資格が得られます。
また、企業への就職の際にも、理系技術職・研究職の採用基準は修士以上となっているケースが多いため、大学院を修了することで専門職を目指しやすくなるでしょう。
3-2 社会に出てから役立つスキルを身に付けられる
2つ目のメリットは、社会に出てから役立つスキルを身に付けられることです。
大学院での研究を通じて、正しい情報を集める力や筋道の通ったレポートを作成するための論理的思考力が身に付きます。これらは社会人として活躍する際に大切なスキルであり、学生のうちに習得できれば大きな強みになるでしょう。
論理的思考力については、以下の記事で詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。
論理的思考(ロジカルシンキング)とは?重要性や身に付ける方法を解説
実践的に論理思考力について学びたい人はMy CareerStudyの「論理的思考トレーニング講座ー思考編ー」も併せてご利用ください。
3-3 初任給が学部卒よりも高い傾向にある
3つ目のメリットは、初任給が大学の学部卒よりも高い傾向にあることです。
大学院では、学部での学びよりも専門的な内容を学び・研究するため、企業は専門性の高い人材として評価します。その評価が給与という形で反映されるため、学部卒よりも給与は高くなる傾向があります。
給与の違いは以下のとおりです。
| 年齢 | 大学卒(千円) | 大学院卒(千円) |
|---|---|---|
| 20~24 | 233.6 | 257.1 |
| 25~29 | 265.2 | 287.1 |
ただし、大学の学部を卒業した人のほうが早く就職し給与を得ているため、企業や職種にもよりますが、全体の収入を見てみると大学院卒のほうが高いとは一概には言いきれません。
3-4 学校推薦や教授推薦を受けやすくなる
4つ目のメリットは、学校推薦や教授推薦が受けやすくなることです。
大学や教授個人が持っているコネクションで企業に学生を推薦することを、学校推薦・教授推薦といいます。研究への姿勢、専門性や知識の習得度合いをみて、企業に優秀な学生を推薦する仕組みです。
推薦による内定率は通常エントリー時よりも高い傾向にあり、専門性が活かせる職種につきやすいため、就職活動をスムーズに進められる可能性は高くなります。
4.大学院進学のデメリット

一方、大学院進学のデメリットとしては以下のような点が考えられます。
4-1 金銭的な負担がかかる
1つ目のデメリットは、金銭的な負担がかかることです。
例えば公立の大学院に進学すると、平均して地域内の入学料20万3,500円もしくは地域外の入学料38万1,000円に加え、授業料が1年あたり53万5,800円かかります。
私立の場合は大学院によって金額の設定がさまざまですが、平均して入学金20万1,750円と1年あたりの授業料79万8,400円、施設設備費7万5,600円がかかり、合計すると100万円を超える金額となります。
出典: 文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
なお、金銭的に進学が難しい場合は奨学金制度が活用できます。また、大学で奨学金を借りている学生は、大学院へ在籍中は在学猶予を受けることができ、返還期間が先送りされます。
ただし、奨学金は社会人になってから返還する必要があるので、いずれにしても金銭的な負担がかかることに変わりはなく、金銭面から大学院への進学を断念している人も少なからずいるのが実情です。
4-2 社会に出るのが遅くなる
2つ目は、社会に出るのが遅くなることです。
修士課程であれば2年、博士課程まで進む場合は5年、学部卒の人たちと比べると社会へ出るのが遅くなります。先に社会人として経験を積んでいる学部卒の人たちとビジネススキルの面で差がつき、また年下の先輩や同僚と働くことになるかもしれません。
4-3 就職活動と研究の同時進行が難しい場合がある
3つ目は、就職活動と研究の同時進行が難しい場合があることです。
就職活動を始めるタイミングと修士論文作成の時期が重なるケースがあり、企業研究や自己分析をしながら論文を作成するのは大きな負担です。
いずれも手を抜くことはできない大切なものなので、スケジュールの管理やタイムマネジメントをしっかりとおこなえるかどうかが重要です。
タイムマネジメントについては、以下の講座でわかりやすく解説しています。 タイムマネジメントに自信がないという人はぜひご覧ください。
「やりたいことを実現するためのタイムマネジメント講座」講座はこちら5.大学卒業後に就職するメリット

大学卒業後に就職するメリットは、社会人としての経験を早く積めることです。
経済的に自立し、新鮮な刺激を社会人として得ながら、自己成長をいち早く実感できるでしょう。優秀なビジネスパーソンとの交流を通じて自身で起業したり、海外へ留学したりなど、行動の幅が広がるかもしれません。
6.大学卒業後に就職するデメリット

大学卒業後に就職するデメリットは、専門職に就きづらいことです。
前述したとおり、大学院を修了すると、研究を通じて得た専門性を活かした職につきやすくなります。しかし、学部卒の場合は多くの企業がポテンシャルに重きを置いて採用をおこなうため、学びを直接活かせる専門職につくのは難しいかもしれません。
大学卒業後に専門職へ就職する際は以下の点をおさえておきましょう。
- 特に理系学部の場合は、修士課程を修了しているかどうかが重要
- 大手企業では修士以上を採用条件としていることが多い
- 企業によっては、実務経験を経ることで研究職としてのキャリアを形成することも可能
7. 大学院修了者と学部卒者の就職活動はどう違う?大学院修了者と学部卒者の就職活動はどう違う?

続いて、大学院修了者と学部卒者の就職活動の違いをご紹介します。
7-1 就職活動のタイミング
学士・修士・博士、それぞれの就職活動タイミングは以下のとおりです。
| 項目 | 選考開始日 | 内定日 |
|---|---|---|
| 学士(学部卒) | 卒業年度の6月1日以降 | 卒業年度の10月1日以降 |
| 修士 | 修了年度の6月1日以降 | 修了年度の10月1日以降 |
| 博士 | 明確な定めがなく、早ければ2年目の6月以降 | 明確な定めがなく、早ければ3年目の3月、4月に内定が出される |
学士・修士の就職活動のスケジュールは原則経団連によって定められていますが、博士は該当しません。よって企業が独自に採用活動をおこなうため、優秀な学生と接点を持つために早いタイミングから活動を始めているケースが目立ちます。
また、前述のとおり修士・博士の学生は就職活動と並行して日々の研究や論文作成をおこなう必要があり、場合によっては大学院を中退し就職活動に専念する学生も見受けられます。
院を中退した場合は「既卒」「第二新卒」枠として就職活動をすることが多い傾向にあります。ただし、厚生労働省の「青少年雇用機会確保指針」においては卒業後3年以内は新卒枠で採用するように推奨しているため、企業によっては新卒枠として採用されるケースもあります。
どの枠で採用されるかは実際の募集要項を確認するようにしましょう。
7-2 企業から期待されていること
学部卒者と大学院修了者とでは、企業の期待値が異なります。学部卒者は今後のポテンシャルに期待し採用するケースが多く見受けられます。一方、大学院修了者はこれまでの研究を通じて得た専門性が活かせる職種での活躍が期待され、即戦力性の観点も加味されます。
就職活動では、大学卒業者は自身の今後の伸びしろを、大学院修了者は培ってきた知見や経験をアピールするのがよいでしょう。
8.大学院進学と学部卒就職で迷ったら?進路選択のポイント

大学院進学か学部卒での就職で迷った際には、以下のポイントを中心に検討してみましょう。
8-1 就職活動と大学院進学の両方を視野に入れておく
1つ目のポイントは、就職活動と大学院進学の両方を視野に入れておくことです。
学部卒で就職活動をおこなう場合は、具体的にいつから動き出すのか、大学院進学の場合は、入学するための試験や推薦はいつ頃実施されるのかを把握しましょう。それぞれのスケジュールと具体的なアクションを整理し、全体感をつかんでおくことが重要です。
8-2 どのようなキャリアにしたいかをイメージしておく
2つ目のポイントは、どのようなキャリアを歩みたいかをイメージすることです。
将来どのような仕事につきたいかを考え、大学院での学びが必要であれば進学を選ぶほうがよいですし、社会人経験を積むことで理想とするキャリアに近づけるのであれば早く就職するのがよいでしょう。
自身のキャリアを考える方法については、以下の講座で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
はじめてのキャリアデザインまた、働くイメージをより具体的に持ちたい人は、「シゴトスタイル診断」を活用してみてもよいでしょう。あなたに合った働き方や真逆の仕事がわかるため、今後のキャリアの方向性を考える際の参考にしてみてください。
シゴトスタイル診断8-3 大学院へ行く場合は目的を明確にしておく
3つ目のポイントは、大学院へ進学する場合は目的を明確にすることです。
「まだ就職したくないから」「学歴を良くしたいから」などの安易な理由ではなく、「突き詰めて学びを深めたいことがある」「研究内容を活かしてつきたい仕事がある」など、明確な目的を持つようにしましょう。
学部卒の人が社会人としてビジネス経験を積んで得ているものと同じくらい価値のある学びを習得しようとする前向きな気持ちが大切です。
9.まとめ
大学院へ進学すると、より専門的な学びの機会を得ることができます。就職を選んだ場合はいち早く社会人経験を積み、学生時代とは異なる視点を身に付けて行動の幅を広げられるでしょう。
もしあなたが大学院進学か就職かで悩んでいるなら、My CareerStudyの「大学院進学と就職、それぞれの特徴徹底解析」講座を参考にしてみてください。講座では、実際に大学院を修了した先輩たちの事例などを紹介しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
「大学院進学と就職、それぞれの特徴徹底解析」講座はこちら
執筆:My CareerStudy編集部
My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。
就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。