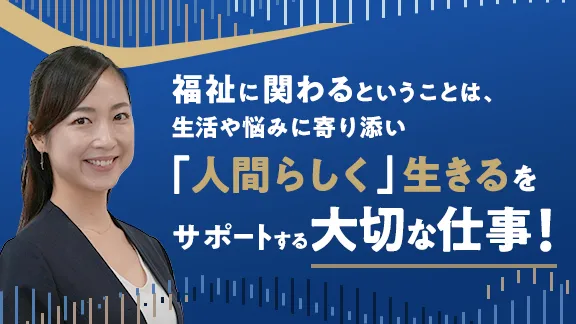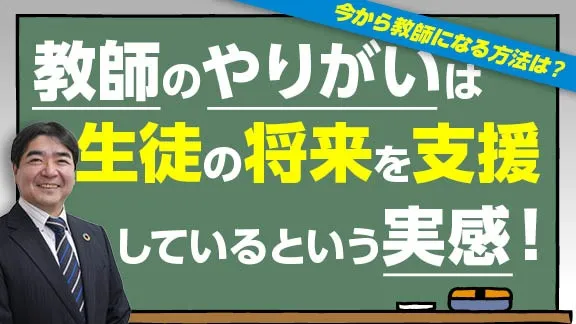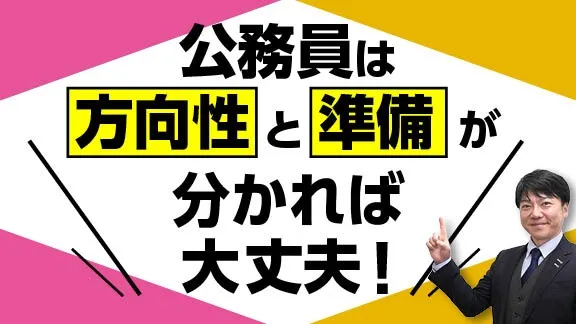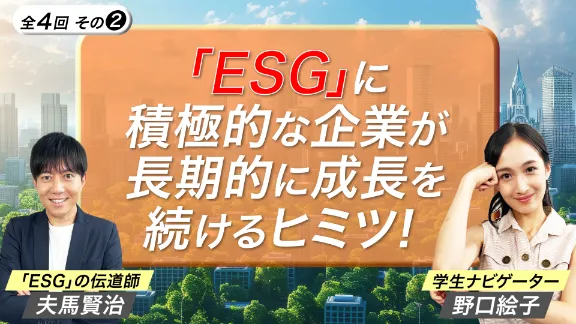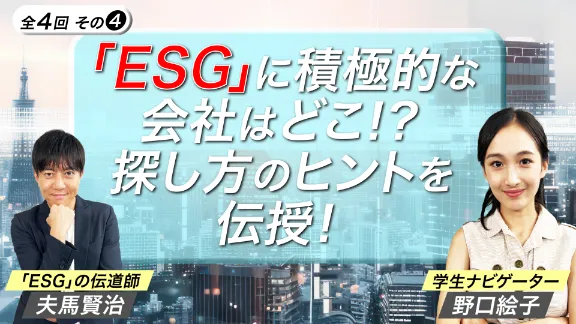社会貢献できる仕事とは?職業の例や話題のSDGs・ESGについてもご紹介
- 公開日
- 2024/12/26
この記事は5分で読めます

「社会貢献」という言葉を目にする、耳にする機会は多いと思います。しかし、具体的にどのような仕事が社会貢献につながるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、社会貢献ができる具体的な職業や、最近目にする機会が多いESGやSDGsと社会貢献の関係性などを解説します。
My CareerStudyの動画講座ではアカウント登録をすることで誰でも無料で社会で役立つ知識やスキルを身につけることができます。
目次
1.そもそも社会貢献とは?

前提として、社会貢献とは「社会をよりよくするための行動全般」を指し、個人や団体、企業が社会のためにおこなう行動全般が該当します。
個人や団体がおこなう社会貢献の例としては、ゴミ拾いのように環境を守るための活動、災害被災地での支援、子どもやお年寄り向けの施設を充実させるための募金活動などが挙げられます。
また、企業が社会のためにおこなう行動はCSR(Corporate Social Responsibility)と呼ばれ、一般的には「企業の社会的責任」と訳されます。例えば、環境に配慮した製品開発を心がけたり、人権侵害を防止する活動に取り組んだりするなどが挙げられます。このように、CSRとは企業が社会や環境に配慮しながら企業活動をおこなうことを指します。
一方で、この記事でご紹介する「社会貢献ができる仕事」とは、業務そのものが直接的に社会の課題解決や人々の生活向上につながる職種を指します。
つまり、CSRは企業全体の取り組みであるのに対し、社会貢献度の高い仕事は個々の職業や業務内容に焦点を当てている点が両者の違いです。
2.社会貢献ができる仕事とは?具体的な職業例も紹介

では、社会貢献につながる仕事にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、代表的な職業の例を挙げてご紹介します。
①医療や看護に関わる仕事
少子高齢化がますます進んでいくと予想される日本において、医療や看護に関わる仕事には大きな社会的価値があります。
総務省の統計によると、2024年9月時点の日本の65歳以上の人口割合は29.3%と世界(人口10万以上の200の国および地域中)で最も高く、医療・看護に対するニーズは今後さらに増加すると考えられます。
医療・看護に関わる職業例としては、医者、介護士、理学療法士、作業療法士、放射線技師などが挙げられます。人の命に関わる仕事であり、これらの職業に就くためには国家資格試験、都道府県認定資格試験、医療関係団体資格試験など、さまざまな試験に合格する必要があります。
参照:公益社団法人全日本病院協会「みんなの医療ガイド-医療関連の資格」
参照:総務省「統計からみた我が国の高齢者(令和6年9月15日)」
My CareerStudyでは、以下の講座で福祉や看護の仕事について詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
②教育や保育に関わる仕事
教育や保育に関わる仕事は、日本の将来を担う子どもに関わる仕事であり、社会貢献の意味でも大きな役割を担っています。
職業例としては、以下が挙げられます。
- 保育士
- 幼稚園教諭
- ベビーシッター
- 小学校・中学校・高校の教師
- 大学教授
- 塾・予備校講師
教師になるには国家資格が必要です。しかし、なかには資格がなくても就ける職業もあります。例えばベビーシッターの場合は、認定ベビーシッターなどの民間資格はあるものの、資格がなければ就けないというわけではありません。
My CareerStudyでは、以下の講座で教師の仕事や教師になるための方法をご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
③暮らしや安全に関わる仕事
地域の安全や人々の暮らしを守る仕事は社会貢献度が高く、やりがいを感じられます。
職業例としては、以下が挙げられます。
- 警察官
- 消防士
- 弁護士
- 自衛隊
例えば消防士は火災や災害などの現場で消火活動や救助にあたるほか、防災の啓蒙・予防活動を通じて人々の暮らしや安全を守っています。弁護士は法律のプロとして、依頼人の正当な権利を守る仕事をしています。「困っている人の役に立ちたい」という気持ちを仕事に活かせる職業です。
なかには国家公務員試験や都道府県・自治体が実施している試験に合格することが条件になっている職種もあるため、調べておくとよいでしょう。
④国や地方自治体に関わる仕事
国や地方自治体で働く人は、国家公務員や地方公務員と呼ばれます。国家公務員は国の機関や中央官庁に属して国全体に関わる政策の立案などをおこないます。一方、地方公務員は地方自治体に属して地域の行政サービスに関わります。
職業例としては、国家公務員は国の各省庁の職員や裁判官、検察官、国会議員などが該当します。地方公務員は各都道府県や市町村の知事、職員などが挙げられます。自分の国や住んでいる地域をもっとよくしたいという前向きな気持ちを仕事にできる職業です。
基本的に、公務員として働くには公務員試験に合格する必要があります。ただし、裁判官や検察官の場合は司法試験への合格が条件になるなど公務員の種類によっても異なります。
公務員の仕事に興味がある場合は、My CareerStudyの以下の講座もぜひ参考にしてください。
⑤国際社会に関わる仕事
国際社会に関わりたい場合には、国際公務員やNPO法人の職員として働く方法があります。
国際公務員は、国連や世界銀行、ユニセフ、世界貿易機関(WTO)などが該当し、世界規模でよりよい社会を築くための活動を各国と連携しておこないます。
なお、国際公務員になるには一般的に大学院卒業以上の学歴が必要で、医学や農学、法学、経済学など専門分野の知識が求められます。
NPO法人とは、営利を目的とせず社会貢献活動をおこなう「特定非営利活動法人」のことで、福祉や教育、街づくり、国際協力など幅広い分野で活動しています。
厚生労働省の情報によると大学卒業者が多く、中途採用で入職するケースが多く見受けられます。仕事内容は、新規事業の企画・立案と事業運営の大きく2つに分けられ、PowerPoint・Word・Excelなど資料作成や表計算といったドキュメント作成能力以外にも、論理的思考力などが高い水準で求められる傾向にあります。
新卒でNPO法人に入職する場合、NPO法人が開催しているインターンシップやボランティア活動で実務を学ぶ機会も多く提供されているので、興味がある人はチェックしましょう。
国際公務員やNPO法人は、外国語の能力を活かしたい、グローバルに活動したい、異文化に興味・関心があるなど、より広い分野で活躍したい人におすすめの職業といえます。
国際社会に関わる仕事がしたい人は以下の講座も参考にしてみましょう。実際に新卒で海外就職した社会人の体験談を交えながら、海外でのキャリア形成について紹介しています。
3.話題の「ESG・SDGs」とは?社会貢献とどう関係がある?

最近、ニュースなどで目にする機会が多い「ESG」や「SDGs」。これらも社会貢献と密接な関係があります。
ESGは「Environment(環境)」・「Social(社会)」・「Governance(ガバナンス=企業統治)」の頭文字を取った言葉で、企業が長期的・持続的に成長するうえで必要な経営観点などを指します。一方、SDGsは、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略語で、2030年までに持続可能でよりよい世界の実現を目指すという国際的な目標です。
ここからは、「ESG」や「SDGs」が社会貢献とどう関わっているか詳しく見ていきましょう。
①ESGと社会貢献の関係
ESGは前述のとおり、企業が成長を実現するうえで重視すべき観点(環境・社会・企業統治)を整理したものです。
各観点について、もう少し具体的に見ていきましょう。
| 観点 | 概要説明 |
|---|---|
| Environment(環境) | 企業が取り組むべき環境問題を指す |
| Social(社会) | 人権問題や男女差別、労働基準など社会全体で取り組むべき問題を指す |
| Governance(企業統治) | 不祥事の防止、信頼性の向上などを指す |
Environment(環境)の観点の例として、企業が製品を開発する過程で、二酸化炭素が多く発生しているとします。
この場合、目先の利益を追求してこの問題から目を背けてしまうと、地球温暖化などのリスクが高まり、地球環境の悪化に加担してしまうことになります。一方で、企業がESGに配慮した経営をおこなっていれば、気候変動による異常気象や災害の発生リスクを考慮した中長期的な発展を目指すことができます。結果的に、地球環境を守るという社会貢献にもつながります。
Social(社会)の観点では、昨今、女性管理職の比率を向上させる取り組みがニュースなどで報じられています。これは、女性がより働きやすく、キャリアアップを目指しやすい環境を促進することを目的としたもので、仕事における不当な男女差別をなくす試みです。
Governance(企業統治)の観点では、製品データの改ざんなどの不正を防ぎ、信頼できるサービスを社会へ提供することが重要とされています。
例えば、社内のルールや仕組みをチェックするための専門部署を作ったり、不正がないかを確認するための調査を実施したりします。また、従業員が困ったことを気軽に相談できる窓口を整備する取り組み(内部通報制度)もその一つです。
これらの取り組みにより、さまざまな観点から不正を防止し、信頼される企業を目指すことが持続的な発展につながるとされています。
ESGの概要や注目される背景・理由をより詳しく学びたい人は、以下の講座もぜひご覧ください。
参考:内閣府「ESGとは何か」
②SDGsと社会貢献の関係
SDGsは、貧困の解消、気候変動への有効な対策、エネルギー資源の有効活用、平和的な社会の実現などを目指して採択された世界共通の17の目標です。これらの目標は「誰一人取り残さない(leave no one behind)」という理念のもと、すべての人々が平等に豊かな未来を享受できるようにすることを目指しています。
日本では、国や企業が問題に直面する国や地域を支援する一方、国内でもすべての人々が豊かな生活を実現するために、さまざまな取り組みをおこなっています。
SDGsは、広い視野で見た際に社会貢献につながる取り組み目標として掲げられています。SDGsの考えが浸透すれば、貧困に悩む国や、日々の生活に苦しむ人々を助け、よりよい世界を築いていく結果につながるでしょう。
4.社会貢献度の高い仕事をするメリット

ここからは、社会貢献度の高い仕事における5つのメリットをご紹介します。
①大きなやりがいを感じられる
まずは、社会貢献というやりがいを感じられることがメリットとして挙げられます。人から感謝を受け取ることや社会的影響のある仕事に関わることで、達成感や充実感を得やすいのが特徴です。自分の仕事に対する自信を持てるため、日々意欲的に仕事に取り組めるでしょう。
②将来的に長く続けられる
社会貢献度の高い仕事は、それだけ社会から必要とされる仕事であるともいえます。そのため需要が高く、将来的に長く続けられる可能性が高いでしょう。
例えば、医療や看護に関わる仕事は、生活していくうえでほとんどの人が必要とするものです。特に日本では少子高齢化が進んでおり、医療・看護が担う役割は今後ますます大きくなると考えられます。経験を積むなかで自身のスキルを高めれば、社会により貢献するチャンスも増えるでしょう。
③現在の社会情勢について詳しくなれる
社会貢献度の高い仕事に就くと、何が社会の課題となっているのか、その課題に対してどのような取り組みがおこなわれているのかなど、社会情勢に対するアンテナを高く張ることができます。
ニュースを見ているだけでは知り得ない、現場にいるからこその質の高い情報を得ることで、自らの知識やスキルをより高め、成長につなげることができるでしょう。
④社会において役立つスキルや知識を身に付けられる
さまざまな人と協力して貧困や教育、医療などの問題に取り組むことで、課題の本質を見抜く力や課題解決能力、コミュニケーションスキルなど社会で役立つスキルが身に付きます。また、問題を解決するためにはその分野に関する知識が必要となり、幅広い専門知識も身に付くでしょう。
仕事のなかで学んだ知見を活かして、将来的に自身で事業を立ち上げるなどの機会も生まれるかもしれません。
⑤キャリアの選択肢が広がる
社会貢献という大きなテーマに挑戦すると、自身のキャリアの選択肢を広げられる可能性があります。
例えば医療看護の分野で仕事をする場合、医療・看護の現場で培った経験を活かして、国内の医療・看護の発展に貢献するといった方法も考えられます。
また、培った専門知識を活かして将来的には自身でNPO法人を立ち上げ、発展途上国の医療・看護を支援することもキャリアの選択肢として考えられるでしょう。
社会貢献は、日本だけではなく、世界的に見ても価値の高い取り組みであり、キャリアを通じて実現したいことの幅を広げられます。
5.まとめ
よりよい社会を実現するための行動すべてが社会貢献活動に該当します。この記事では、代表的な社会貢献につながる仕事を紹介しましたが、これ以外にも社会に貢献できる仕事は数多く存在しています。実際に行動してみたいという場合は、地域のゴミ拾いや募金活動への協力など、身近に参加できることから始めてみるのがおすすめです。そのなかで得た学びや気付きを、キャリアを通じて達成したい目標や夢に結び付けて考えてみましょう。
特に大学生の皆さんは、自由度の高い大学生活の時間をうまく活用すれば、社会貢献活動に取り組むなかで社会と多くの接点を持つことができます。そして、自身が将来どのようなキャリアを実現したいのかを考える大きなきっかけにもなるはずです。

執筆:My CareerStudy編集部
My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。
就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。