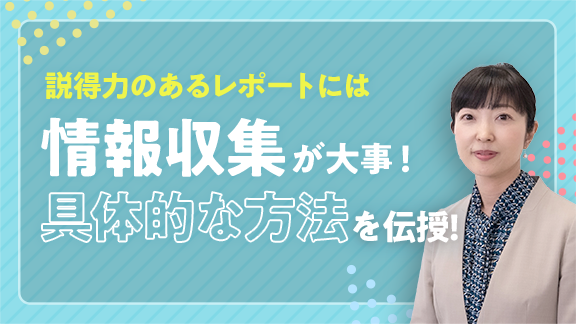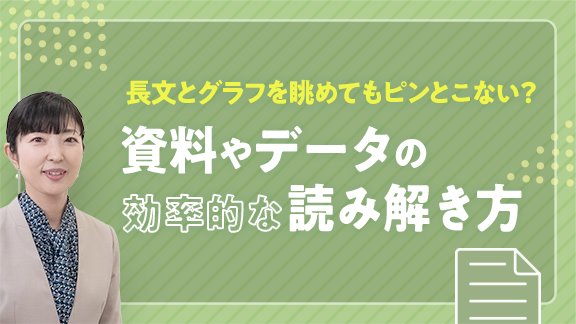大学レポート・論文の考察の書き方は?ポイントと注意点をわかりやすく紹介
- 公開日
- 2024/11/29
この記事は5分で読めます

大学生になると、講義の学びや研究結果などをまとめるためにレポートや論文の執筆を求められることがあります。そのなかでも考察は、結果に対する自分自身の考えを言語化するものであり、レポートや論文内で重要な役割を担います。
この記事では、考察とはそもそも何か、レポートや論文のなかでの位置付け、書き方のポイントなどを解説します。
My CareerStudyの動画講座ではアカウント登録をすることで誰でも無料で社会で役立つ知識やスキルを身につけることができます。
1.そもそも「考察」とは?

考察という言葉には、「物事を明らかにするために、よく調べて考えをめぐらすこと」という意味があります。
つまり考察では、単に事実や調査結果をまとめるだけではなく、得られた情報をもとに自分なりの考えを導き出せているかどうかが求められます。
引用:goo国語辞書「考察(こうさつ) とは? 意味・読み方・使い方(デジタル大辞泉)」
①感想・見解・結果との違い
考察と混同しやすい言葉に「感想」・「見解」・「結果」があります。
「感想」は物事に触れて感じたことや思ったことを意味し、主観的な意味合いが強い言葉です。一方「考察」は、実験や調査を通じて見えてきたことや考えられることを紐解いていくため、客観的な要素をベースとしている点で違いがあります。
「見解」は、物事に対する考え方や価値判断を意味し、自身が導き出した答えを「自分の考え」として明示する意味合いがあります。一方「考察」は、考えることそのものを指します。
「結果」は、ある原因や行為から生じた結末や状態を意味します。自身の考えを反映させず、ただ事実を明確にするのが結果です。一方「考察」は、結果をもとに分析などをおこなう点で異なります。
出典:goo国語辞書「感想(かんそう) とは? 意味・読み方・使い方(デジタル大辞泉)」
②レポート・論文での考察の位置付け
大学生活においてレポートや論文に触れる機会は多く、講義によっては自身で執筆する場合もあるでしょう。
「考察」という言葉の意味を踏まえると、大学のレポートや論文における考察とは、文献調査や実験などで得られた結果について自分自身の言葉で整理して、考えたことや明らかになったことを述べることといえます。
ちなみに、レポートと論文の違いは「テーマ設定の方法」にあります。レポートの場合は講義内容に合ったテーマを与えられることが多く、論文の場合は自身でテーマを設定するケースが多いでしょう。
レポート・論文ともに、自身の考えをもとに仮説を設定したあとに客観的な事実を記載します。そして、その結果を紐解き、仮説と比較しながら、どうしてそのような考えに至ったのかを考察として記載します。導き出された結果が何を意味するのか、自身の考えと合わせて明確にするのがポイントです。
レポートや論文の基本的な構成や書き方のコツを詳しく知りたい場合は、My CareerStudyの以下の講座をぜひ受講してみてください。
また、評価されるレポートを作成するコツは以下の記事でもご紹介しています。これからレポート作成をおこなう人はこちらも併せてご覧ください。
2.大学のレポート・論文で考察が重要な理由は?

レポートや論文をまとめるうえで考察が欠けていると、明らかにした結果を単に記載しただけのものになってしまいます。
しかし、自分なりの視点でその結果を紐解くことで、これまでになかった観点で結果を見つめ直せたり、既存の研究の問題点に気付けたりと、より価値のあるレポート・論文に仕上げることができます。
考察は、自分なりの仮説を立てて検証し、何を学び得たのかを明確にするうえで重要な要素です。考察をしっかりおこなうことで、レポートや論文の内容がより深くなり、読者に「なるほど」と思ってもらいやすくなります。よい考察が書ければ、レポートや論文の価値はより高まるでしょう。
3.評価される考察の書き方

ここからは、高く評価される考察の書き方について具体的に解説していきます。
STEP1:研究・調査結果を自分で解釈する
最初に、自身がおこなった研究や調査の結果を自分なりに解釈して言語化します。
例えば、「紙媒体と電子書籍化の動向」というテーマのレポートを課せられたとしましょう。
そこで、公益社団法人 全国出版協会の調査データを分析したところ、「2018年以降の紙市場は縮小・電子出版市場は拡大傾向となっている」ことがわかりました。また、日本新聞協会のデータを分析した結果、「紙媒体である新聞の発行部数は2005年から2023年まで19年連続で減少している」ことがわかりました。
それを踏まえて、なぜ継続的に紙市場が縮小しているのかについて「インターネットやスマートフォンなどの普及によって情報を得る手段が多角化しており、利便性・効率性の観点から紙媒体の必要性が減っているためではないか」と解釈できます。
出典:一般社団法人 日本新聞協会「新聞の発行部数と世帯数の推移
出典:公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所「出版指標 2024年1が25日」
なお、どのように自分のテーマに合った情報を収集すればよいのかわからない人は、My CareerStudyの以下の講座もぜひ参考にしてみてください。
STEP2:結果と先行研究を関連付ける
次に、前述した新聞の発行部数が年々減少していることや、紙市場が縮小しているという調査結果と先行研究を関連付け、結果と先行研究の内容に矛盾があるのか、それとも合理的な結果なのか記載します。
具体的には、STEP1で立てた「電子デバイスよりも利便性・効率性面で劣るため、紙媒体の必要性は下がっていく」という解釈に対して、その分野における一般的な認識や先行研究の内容と比較していきます。可能な限り客観的に比較するためにも、さまざまな研究と比較することが大切です。
例えば、先行研究で以下のような内容が述べられていたとしましょう。
電子書籍やデジタルメディアの普及により紙市場が縮小すると予測されている一方、書籍や雑誌には紙媒体特有の価値があるため紙市場は維持される。
先行研究で述べられている「紙媒体市場の縮小」という点は仮説と合致していますが、「市場自体は維持される」という点は合致しません。
このように、自分自身の結果と先行研究の内容が必ずしも一致するというわけではありません。この場合は、「紙媒体特有の価値」というのがどのようなものなのか、それが紙市場の維持とどう関係しているのかなどを分析し、意見が合致しない理由を記載します。
STEP3:実施した研究・調査の限界を記載する
次に、研究の限界を記載します。
研究の限界とは、自分の研究では明らかにできない事象や研究結果の解釈に影響を与える可能性がある制約を指します。研究の問題を自身も認識しており、完璧な研究結果ではないと自ら公表することで、信頼性の向上につなげられる可能性があります。
STEP4:今後の展望について記載する
最後に研究の限界などで言及されている課題を解決するためにどうすればよいかをまとめることで、今後の研究につなげられます。
また、このテーマであれば、今後紙媒体はさらに減少していくのか、一定の市場を維持し続けるのかについて、なぜそう考えるのか、自分の言葉で言及できればよりよい考察になるでしょう。
4.考察を書く際に意識したいポイント

最後に、考察を書く際に意識したいポイントを4つご紹介します。
①結果に基づく内容のみを記載する
考察とは、「結果から客観的に解釈できる自身の意見」です。レポートや論文内に出てこない事象や主観を交えた感想を書くと、読み手が混乱してしまいます。
そのため、データでは裏付けられない推測や仮定は記載しないようにしましょう。
②結果と考察を明確に分け、区別する
前述のとおり、結果は研究や調査によって導き出された事実であり、考察は結果に対して自分の考えを明示するものです。結果と考察が入り混じってしまうと、どれが事実でどれが自分の考えなのかがわかりづらくなるので、明確に分けるよう意識しましょう。
③先入観や主観にとらわれず、多角的・論理的に考える
自身の先入観や主観にとらわれてしまうと、考察ではなく感想に近い内容になってしまったり、偏った意見を述べてしまったりする可能性があります。そのため、レポートや論文を執筆する際は、さまざまな先行研究や既存の理論、他の学問的観点などと可能な限り関連付け、多角的・論理的に考えることが大切です。
④曖昧な表現を多用しない
「おそらく」「だと思われる」などの曖昧な表現を多用すると、自身の主張が相手に伝わりづらくなります。また、読み手に「自信がないのか」「しっかり調査をしていないのでは」などネガティブな印象を持たれてしまうかもしれません。
自分の意見や主張を記載する際は、曖昧な表現は控えて言い切るようにしましょう。
5.まとめ
考察は、研究や調査の結果得られた情報をベースに、自分の考えや意見を述べるものです。レポートや論文を通じて何が言いたいのか、その表明であるともいえます。
自身の主観に偏らないように多角的な視点を取り入れると、より内容の濃い考察が書けるはずです。感想や見解など混同しやすい表現と差別化し、正しい書き方を身に付けましょう。

執筆:My CareerStudy編集部
My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。
就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。