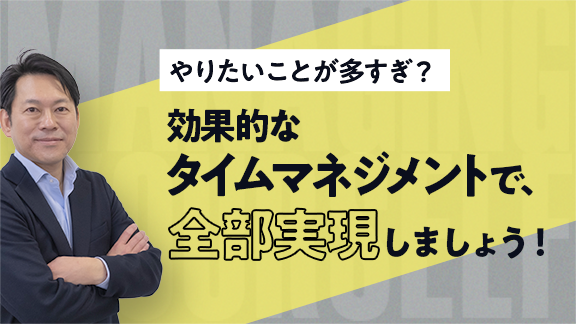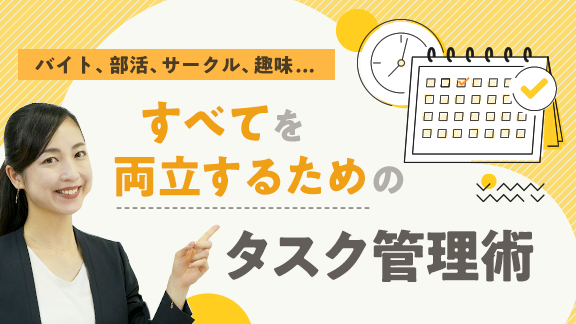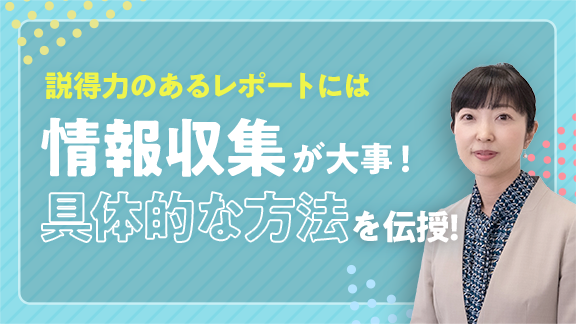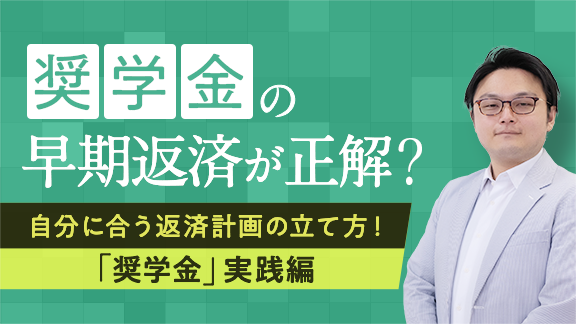大学の時間割はどう組む?上手な組み方や文系・理系別の具体例をご紹介
- 公開日
- 2024/12/13
この記事は5分で読めます

高校までは、学校から時間割を指定されるのが基本でした。しかし、大学生になると自分自身の学びたい内容に合わせて、時間割を自分で組めるようになります。柔軟に時間割を組める反面、卒業に必要な要件に沿ってあなた自身で大学4年間の過ごし方を決めていかなければなりません。
この記事では、大学の時間割を組むうえで押さえておきたいポイントや具体例を交えながら、上手な時間割の組み方をご紹介します。
My CareerStudyの動画講座ではアカウント登録をすることで誰でも無料で社会で役立つ知識やスキルを身につけることができます。
1.大学の時間割を組む前に把握しておくべきこと

まずは、時間割を組む前に押さえておきたい基本的な内容についてご紹介します。
①大学の講義時間
大学の講義時間は、一般的に1コマ90分です。
高校では1時限の時間が50分なので、40分程度講義時間が長くなります。大学によって異なりますが、昼休みまでの午前に2コマ、昼休み以降の午後に3〜4コマ程度の講義を組むことができます。
一般的な講義時間は以下のとおりです。
| 開始時間・終了時間 | 時限 |
|---|---|
| 9:00~10:30 | 1時限目 |
| 10:40~12:10 | 2時限目 |
| 12:10~13:00 | 昼休み |
| 13:00~14:30 | 3時限目 |
| 14:40~16:10 | 4時限目 |
| 16:20~17:50 | 5時限目 |
| 18:00~19:30 | 6時限目 |
②卒業に必要な単位数
大学を卒業するには、4年間で124単位以上を取得する必要があります。
1年間に取得できる単位数はおおよそ40~46単位ほどで、多くの場合、1科目受講完了すれば2単位が得られる仕組みです。
124単位を4年間で取得する場合、1年間で31単位以上の取得が目安になりますが、3年生以降は就職活動や、論文執筆や研究などで忙しくなるため、1年生・2年生の比較的自由時間がある期間に可能な限り多くの単位を取得しておくのがおすすめです。
③講義の内容
講義の内容は、シラバスと呼ばれる各科目の講義計画で確認できます。
講義の時間帯や講義の目的、到達目標などが記載されているので、講義を選ぶ際の参考にしましょう。
また、単位取得に必要な出席率やレポート課題やテストの実施有無など、成績評価に関する詳細情報も掲載されています。
なお、一般社団法人国立大学協会が公開している国立大学のシラバスでは、各国立大学の講義内容が確認できるのでぜひ参考にしてみてください。
④必修科目と自由選択科目
講義の内容は、シラバスと呼ばれる各科目の講義計画で確認できます。
講義の時間帯や講義の目的、到達目標などが記載されているので、講義を選ぶ際の参考にしましょう。
また、単位取得に必要な出席率やレポート課題やテストの実施有無など、成績評価に関する詳細情報も掲載されています。
なお、一般社団法人国立大学協会が公開している国立大学のシラバスでは、各国立大学の講義内容が確認できるのでぜひ参考にしてみてください。
2.大学の時間割の上手な組み方

ここからは、大学の時間割の組み方について解説していきます。
最終的に必要な単位数を修了できるよう各講義で獲得できる単位数を足し算し、4年間で124単位を取得できるように設計しましょう。
①STEP1:まずは必修科目・選択必修科目を組み込む
講義の内容は、シラバスと呼ばれる各科目の講義計画で確認できます。
講義の時間帯や講義の目的、到達目標などが記載されているので、講義を選ぶ際の参考にしましょう。
また、単位取得に必要な出席率やレポート課題やテストの実施有無など、成績評価に関する詳細情報も掲載されています。
なお、一般社団法人国立大学協会が公開している国立大学のシラバスでは、各国立大学の講義内容が確認できるのでぜひ参考にしてみてください。
②STEP2:次に資格課程の講義を組み込む
時間割を組む際は、まず必修科目・選択必修科目から組むようにしましょう。
前述のとおり、必修科目・選択必修科目は卒業要件を満たすために必ず履修する必要がある科目です。例えば、124単位を取得したとしても、必修科目の単位がそのなかに含まれていなければ、卒業できないケースもあります。時間割を組む際には、必修科目の単位数を優先的に意識しましょう。
また、必修科目は履修年度が決まっている場合もあり、決められた年度までに単位が取得できていないと留年になってしまう恐れもあります。そのため、必修科目を時間割に組み込み、あなたの1週間の時間割のベースをつくりましょう。
③STEP3:最後に自由選択科目を組み込む
必須科目と資格課程の講義を時間割に組み込んだら、最後に卒業に必要な残りの単位数を自由選択科目で確保できるようにしましょう。
自由選択科目は、知識の幅を広げたり学びを深めたりするという点で役立つ講義も多いので、興味のある科目は積極的に受講してみましょう。
人気の自由選択科目は抽選制や先着順になっていることも多く、希望しても講義が受けられない場合があります。いつ抽選がおこなわれ、結果はいつわかるのかなどをシラバスで確認しましょう。
3.大学生活を充実させるためのアドバイス

大学生活を充実させるうえで大切なのは、無理のない時間割を組むことです。
ここでは、5つのポイントをご紹介します。
①低学年のうちにしっかり単位を取得する
1年生、2年生のうちにしっかり単位を取得し、余裕をもって3年生、4年生を迎えられるようにしましょう。
前述のとおり高学年になると、ゼミや卒業論文の執筆、インターンシップ・仕事体験への参加、就職活動の開始などで忙しくなります。
必要な単位を取得できていない場合、大学卒業に対するプレッシャーを感じてしまうかもしれません。低学年のうちにしっかり単位を取得し、3年生、4年生の時間を有意義に過ごせるようにしましょう。
②生活スタイルに応じて1日のコマ数を調整する
一日に講義を詰め込みすぎて無理なスケジュールになってしまっていないか、注意が必要です。
一日に多くの講義を詰め込むと予習・復習が追いつかず課題の提出が間に合わなかったり、試験勉強に苦労したりするかもしれません。場合によっては、「勉強が間に合わず単位が取れなかった」といった結果になってしまう恐れもあります。
また、遅い時間に多くの講義を詰め込んでしまうと、アルバイトやサークルなどの活動時間を確保できなくなる可能性もあるでしょう。
こうした事態にならないよう、時間割を決める際は自分の生活スタイルに合わせて一定の余裕を残すことも意識してみましょう。
資格取得の科目は5時限・6時限など遅い時間に実施されるケースもあるため、その際は翌日の1時限目には講義を入れないというのも手です。
③空きコマは有意義に活用する
一日に講義を詰め込みすぎて無理なスケジュールになってしまっていないか、注意が必要です。
一日に多くの講義を詰め込むと予習・復習が追いつかず課題の提出が間に合わなかったり、試験勉強に苦労したりするかもしれません。場合によっては、「勉強が間に合わず単位が取れなかった」といった結果になってしまう恐れもあります。
また、遅い時間に多くの講義を詰め込んでしまうと、アルバイトやサークルなどの活動時間を確保できなくなる可能性もあるでしょう。
こうした事態にならないよう、時間割を決める際は自分の生活スタイルに合わせて一定の余裕を残すことも意識してみましょう。
資格取得の科目は5時限・6時限など遅い時間に実施されるケースもあるため、その際は翌日の1時限目には講義を入れないというのも手です。
④休憩時間は移動や復習時間に充てる
各コマの間には10分程度の休憩時間が設けられています。
講義によって教室が異なる場合も多いため、移動だけで休憩時間が終わってしまうこともあるかもしれません。もしも次の授業開始までに余裕があれば、前回の講義の復習に充てるとよいでしょう。
アルバイトやサークル活動など、勉強以外にも積極的に取り組みたい人は、ぜひ休憩時間を有効活用してみてください。社会人になってからも役に立つ「タイムマネジメント力」が身に付けられるはずです。
タイムマネジメントについて、実践的に身に付けたい人や興味がある人はぜひ以下の講座を受講してみてください。
⑤ツールを活用して時間割を管理する
手帳で時間割を管理するのもよいですが、アプリやツールなら柔軟に時間割を組み直すことができます。
ツールを活用すれば各課題の締め切りやテストの日程などの情報を一元管理できるため、見落としを防ぎやすくなります。大学生活では、アルバイトや部活動・サークル活動など講義以外の課外活動に取り組むことも多く、それぞれのスケジュール管理も大変です。しかし、ツールを使うことで視覚的にわかりやすく予定を確認でき、効率的に時間を配分できるようになります。
また、サークルやゼミなど大勢のメンバーでスケジュールを調整する場合には、同じツール上で予定を共有し合うことでスムーズに日程調整ができるでしょう。
大学生向けのタスク管理ツール例やその活用方法については、以下の講座でご紹介しています。
4.【具体例】参考にしてみよう!文系・理系別の時間割

最後に、時間割の具体例をご紹介します。時間割を組む際に意識したこともまとめていますので、ぜひ時間割を組む際の参考にしてみてください。
①文系文学部1年生Aさんの時間割例
まずは、文系文学部1年生のAさんの時間割を見てみましょう。

Aさんは、時間割を組む際に以下の点を意識しているようです。
- 朝が苦手なので、なるべく1限目に講義を入れないようにした。
- 水曜日は講義を入れず、タスクや課題、資格の勉強などをする日とした。
- 空きコマをなるべく作らないことで、勉強する時間帯には集中して取り組み、その他の時間帯は遊びやアルバイトに使うことで、メリハリのある生活を心がけた。
- 英語を学ぶうえで大事な技能を効率的に学べるよう、さまざまなスタイルの英語講義を入れた。
- 学年が上がるにつれて余裕を持てるように、必要な単位数を確実に取得できるように調整した。
- オンデマンド授業(受講日や時間が決まってないため時間割上には記載なし)を取ることで、余裕がある時間を有効活用できるようにした。
アルバイトやサークル活動など学業以外にも積極的に取り組みたい人や、すきま時間を有効活用したいという人はぜひ参考にしてみましょう。
②理系工学部2年生Bさんの時間割例
次に、理系工学部2年生のBさんの時間割を見てみましょう。

Bさんは、時間割を組む際に以下の点を意識しているようです。
- オンデマンド授業の「電子回路」や「計算機工学I」を入れることで、効率的に学習できるようにした。
- 午前か午後が休みの日を作り、バイトや趣味の時間を確保するようにした。
- 自分の興味がある分野を見つけて、今後の研究室選びの参考にするために、学科の授業を多く入れた。
5.まとめ
大学では卒業に必要な単位数が定められていたり、必修科目や自由選択科目があったりするため、少し複雑に感じるかもしれません。
しかし、時間割を組んで計画的に生活することで得られるタイムマネジメント力やタスク管理のスキルは社会人になってからも役立ちます。
My CareerStudyが提供している以下の講座も参考に、充実した大学生活を過ごすための一歩として、自分に合った時間割を組めるよう挑戦してみましょう。

執筆:My CareerStudy編集部
My CareerStudyは学生に向けた社会で役立つ知識やスキルを提供するキャリア学習サービスです。
就活やインターンシップ、学生生活に活かせる情報を発信しています。